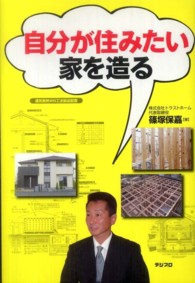内容説明
淑徳大学人文学部開設記念「風土記撰上1300年」シンポジウム。古代人にとって、蛇とはどんな存在だったのか?出雲の国はどうやってつくられたのか?浦島太郎の物語はいつごろつくられたのか?常陸国、出雲国、丹後国の風土記に伝わる説話の謎を解き明かす。
目次
第1章 『風土記』とは何か(『風土記』撰上;「風土記」という名称 ほか)
第2章 麻多智伝承と常陸の蛇神(箭括氏麻多智;壬生連麿 ほか)
第3章 『出雲国風土記』の世界(新羅からの国引き;「北門」からの国引き ほか)
第4章 『丹後国風土記』の神仙説話―浦島子と天女(浦島子伝説;天女伝承 ほか)
著者等紹介
宇佐美正利[ウサミマサトシ]
群馬県出身。明治大学大学院文学研究科史学専攻博士課程単位取得退学。淑徳大学人文学部教授・学部長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
8
「『常陸国風土記』…兄と妹がいます。妹のもとに名の知れない男が通ってきて、やがてその妹が子どもを産む…その子どもが蛇だった…その蛇は神様、大和の三輪山の神に代表される…その蛇がやがて天に昇ろうと…付き人を求めるのですが、それが拒否されると、怨んで伯父を殺してしまう…伯父を殺しながら天に昇っていこうとする。あわてて、母親である妹が土器(盆)、これは蛇が住んでいたベビーベッドのようなものですが、この盆を蛇に投げつけると、蛇神に当たって、天に昇れなくなってしまった。盆に憑依させられてしまったわけです」2018/08/27