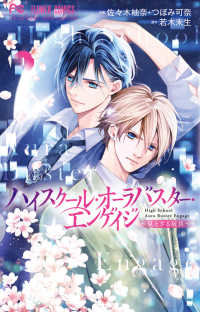出版社内容情報
なぜ住宅は「社会的」なものなのか 住宅観・住宅構想の変遷と、民間零細借家、社宅、市営住宅、橋下の住宅、そして、ホームレス向け簡易宿舎での住民の日常生活や抵抗・反対運動の事例から考える。 第1部 「住宅の社会性」を重視する社会とそうでない社会(近世~現代日本の住宅保障史;比較理論からみた「日本型」住宅政策;貧困救済の担い手と住宅問題―一九一〇~二〇年代の大阪府方面委員の活動;第二次大戦後の難民の統合から今日のソーシャル・ワーカー雇用まで―ドイツ・ゾーリンゲン貯蓄建設組合の活動―[講演会記録];一九世紀アーヘンの住宅建設運動とキリスト教理念)
住宅観・住宅構想の変遷と、民間零細借家、社宅、市営住宅、橋下の住宅、そして、ホームレス向け簡易宿舎での住民の日常生活や抵抗・反対運動の事例から考える。
地域社会の形成にとって重要だったのは住民や関係者の「積極的」な関与だけではない。戦後日本の「橋下」住宅を訪問する警察官、学校の先生、民間零細借家における家主、ドイツの市営住宅に住む身体的、精神的障がいを持つ高齢の女性住民の「消極的」な関与もまた、地域社会の形成に欠かせぬ要素となった。
【目次】
は じ め に
第Ⅰ部 「住宅の社会性」を重視する社会とそうでない社会
第1章 近世~現代日本の住宅保障史 木下光生
第1節 住まいの保障に冷たい現代日本社会
第2節 「普通の家」と近世の住宅保障
第3節 「自助・市場・小屋」の伝統を受け継ぐ近現代の住宅保障
第2章 比較理論からみた「日本型」住宅政策 平山洋介
第1節 福祉国家の「ふらつく柱」
第2節 福祉レジームと住宅
第3節 デュアリズムとその「修正」
第4節 イースト/ウエスト
第5節 広域化する新自由主義
第6節 分岐と収束
第3章 貧困救済の担い手と住宅問題 飯田直樹
──一九一〇~二〇年代の大阪府方面委員の活動──
第1節 大阪府方面委員制度とは
第2節 方面委員手帳に記された田中半治郎の活動
第3節 部落事務員小寺正吉による「住宅改善」
第4節 方面委員の役割──救済機関の調査・講究
第4章 第二次大戦後の難民の統合から今日のソーシャル・ワーカー雇用まで マンフレッド・クラウゼ(永山のどか 訳)
──ドイツ・ゾーリンゲン貯蓄建設組合の活動── [講演会記録]
第1節 住宅供給組織と難民の統合
第2節 高齢社会における住宅供給組織の役割
第5章 一九世紀アーヘンの住宅建設運動とキリスト教理念 平松英人
第1節 一九世紀前半のドイツ都市
第2節 一九世紀前半の都市アーヘン
第3節 「社会問題」とキリスト教理念
第4節 カリタスと市民的連帯
第Ⅱ部 地域社会形成における住宅の役割の強さ・弱さ
第6章 都市の公共住宅計画の総合性と地域社会概念 黒石いずみ
──関東大震災後から第二次大戦後まで──
第1節 一元化テーゼと都市計画・住宅計画の歴史的分離
第2節 同潤会と中村寛
第3節 伊部貞吉の土地区画整理論
第4節 営団と西山夘三の計画論と地域の位置づけ
第5節 戦 後から一九六〇年代にかけての住宅政策と日本住宅公団の展開
第6節 一元化テーゼをめぐる計画思想の歴史が意味するもの
第7章 三井三池炭鉱における社宅と主婦会 チェルシー・センディ・シーダー
──労働と暮らしと地域のコミュニティ──
第1節 労働の暮らし、暮らしの労働
第2節 男性鉱山労働力の形成と社宅の誕生
第3節 戦後労働のジェンダー構造と主婦会の誕生
第4節 社宅と主婦ぐるみ闘争としての一九六〇年三池争議
第5節 三井三池CO裁判をケア・ワークの承認要求として
第6節 労働と暮らしと地域の遺産としての三池社宅内容説明
目次
第2部 地域社会形成における住宅の役割の強さ・弱さ(都市の公共住宅計画の総合性と地域社会概念―関東大震災後から第二次大戦後まで;三井三池炭鉱における社宅と主婦会―労働と暮らしと地域のコミュニティ;第二次大戦後の民間賃貸住宅の零細家主と借家関係の変容;「不法居住」地での地域社会形成―戦後京都における橋下住民;ホームレス状態にある人々への居住支援と地域社会形成;市営住宅団地と地域社会の形成―二〇世紀後半西ドイツ・シュツットガルト市の場合)