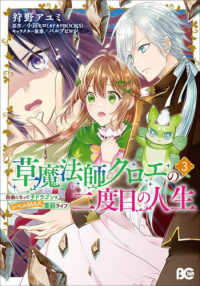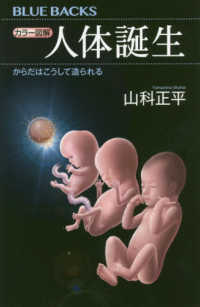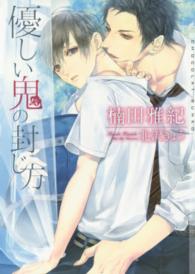目次
第1部 試合中のジレンマ―意図的なルール違反は許されるのか?(郷に入っては郷に従うべきなのか?;バスケットボールのファウル・ゲームは許されるのか?;サッカーのトラッシュトークは許されるのか?;野球の報復死球は許されるのか?)
第2部 練習・試合外のジレンマ―体罰や連帯責任は無用の長物か?(運動部活動における体罰はなぜ受容されるのか?;不祥事に対する対外試合禁止処分は妥当か?;Jリーグの無観客試合処分は妥当か?;スポーツが生み出す差別は許容されるのか?)
著者等紹介
大峰光博[オオミネミツハル]
1981年生まれ。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程修了。現在、名桜大学人間健康学部スポーツ健康学科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
SAHARA
1
運動部活動における体罰の重要の、フロムの権威を求める性格や倫理、良心は参考になる。少年が指導者を求めるのは当たり前では エピローグの芸術やスポーツに限らず、なにかに没頭するうちに日常的倫理から逸脱していってしまうことは、考えないといけないよね。芸術と言ってわいせつ行為をしたり殺人をすることは許されない。それは責任取れないからとか。行き過ぎると、よくないことを知らずしらずのうちにやってしまう可能性があることを自覚すべき。スポーツに限らず、労働とかにもあてはまる(過労死とか)?結局、何事も程々にってことかね。2021/11/29
きぬりん
1
スポーツ倫理の考察。ルールをめぐる形式主義とエトス主義との対立、バスケのファウルゲーム、トラッシュトーク、野球の報復死球、体罰、高校野球不祥事の連帯責任、Jリーグの無観客試合処分等の個別問題や、スポーツそれ自体の差別性の問題が取り扱われている。すでに議論の蓄積のある問題についてはきちんと先行研究が踏まえられているが、そこからの独自考察の展開には肩透かしの感も。議論の蓄積のない問題は、他分野の議論の多少強引な当てはめに終始している印象。何より、まえがきやエピローグの問題意識がうまく昇華されていないのが残念。2021/05/29
hryk
0
いろいろな事例が取り上げられていて勉強になる。2019/10/06
-

- 電子書籍
- スライムテイマーの異世界ライフ11 c…
-
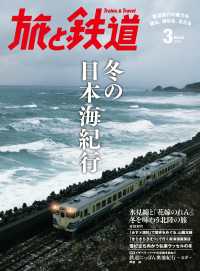
- 電子書籍
- 旅と鉄道 2016年 3月号 冬の日本…