内容説明
「みんな」の文化は存在するのだろうか?インターネット/Jポップ/トレンディドラマ/少年ジャンプ/キャラクターグッズ/オカルト/フォーク・ミュージック…人々が楽しむ文化が描き出す、それぞれの時代の社会意識とは。社会学的視点から、「みんな」の文化としてのポピュラーカルチャーを、それを支える時代意識とともに考える架空の講義録。
目次
第1回 イントロダクション―文化の楽しさ、社会学の楽しさ
第2回 文化≒コミュニケーション―インターネットは「ポピュラーカルチャー」たりえるのか?
第3回 90年代音楽バブルとはなんだったのか?
第4回 トレンディ!な空間
第5回 少年ジャンプの弁証法
第6回 ファンシーが充満する80年代
第7回 あなたの知らない世界―70年代オカルトブームを考える
第8回 「私たちの歌」と「みんなの歌」―フォーク・ソングの変遷
最終回 ふたたび現在のポピュラーカルチャーを考える
著者等紹介
片上平二郎[カタカミヘイジロウ]
1975年東京生まれ。1998年上智大学理工学部化学科卒業。2002年慶應義塾大学大学院社会学研究科社会学専攻(修士課程)修了。2007年立教大学大学院文学研究科比較文明学専攻(博士後期課程)修了。2010年~2015年立教大学文学部文学科文芸思想専修助教。現在、立教大学、法政大学、明星大学兼任講師。理論社会学(主に批判的社会理論)、現代文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 王都の外れの錬金術師【分冊版】 43 …
-
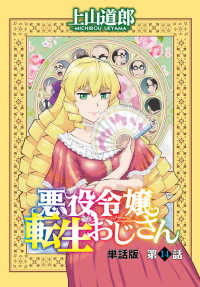
- 電子書籍
- 悪役令嬢転生おじさん 単話版 14話「…
-
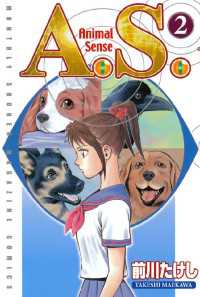
- 電子書籍
- A.S.(2)
-
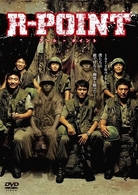
- DVD
- R-POINT
-
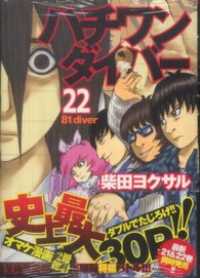
- 電子書籍
- ハチワンダイバー 22 ヤングジャンプ…



