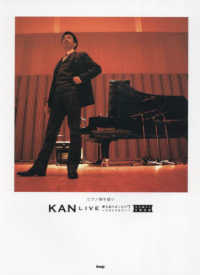内容説明
ソクラテス・プラトンにはじまり西洋2600年の哲学を支配した「主観性の哲学」、プラトニズム。自己ならびに他者に対して常に告発的であらざるをえない主観性の原理は、西洋近代世界を決定づける発端となった。
目次
第1講 ソクラテス(はじめに プラトニズム概説;ソクラテス ほか)
第2講 小ソクラテス学派(アンティステネスとキュニコス派;アリスティッポスとキュレネ派 ほか)
第3講 プラトン(生涯;学説 ほか)
第4講 新プラトン哲学(新プラトン主義への前奏;新プラトン派 ほか)
著者等紹介
日下部吉信[クサカベヨシノブ]
1946年京都府に生まれる。1975年立命館大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文学)。1987‐1988年、1996‐1997年ケルン大学トマス研究所客員研究員。2006‐2007年オックスフォード大学オリエル・カレッジ客員研究員。現在、立命館大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Gokkey
10
冒頭から「プラトニズムは主観性の哲学の一表現」とある。ピュシスを完全に抜き取られた自然哲学の系譜はソクラテス・プラトンによりハイデガーのいう所の「主観性の形而上学」のスタートとなる。この主観性原理は対象志向的にならざるを得ず、必然的に超越的存在(イデア)へと帰結する。これはヘラクレイトスの万物流転説とパルメニデスのアポリアの折衷案として機能するが、この流れはイデアを生み出すさらに上の階層の存在を想定する新プラトン主義を生む。これは後のヘブライズム流入による「神」の居場所を用意しておくこととなった。2020/10/04
roughfractus02
3
自然学φυσικάの後μεταの語義がなぜ形而「上」に変わるのか?著者は自然の運命や不条理から離れ、社会化する都市に生きる哲学者が自然=存在(φύσις)から認識(αναγνώριση)へとテーマをシフトする点に注目する。プラトニズムの中にソクラテスを含める本書は、プラトンの描くソクラテスを歴史上の彼と区別し、自らの影として師を描くプラトンに「宇宙とは何か」から「私とは何か」への転換を見る。ソクラテス、小ソクラテス学派、プラトン、新プラトン哲学への道のりは、認識を存在へ権威拡大するキリスト教中世へ向かう。2017/08/26
Ikkoku-Kan Is Forever..!!
3
初期ギリシア哲学を「『存在』と『主観性原理』の相克と葛藤の修羅場」と捉える筆者は、主観性原理を確立したソクラテス・プラトン哲学を西洋の運命(ゲシック)と呼びこれを断罪する。筆者曰く「イデア的意味対象と主観性の志向性の硬い結合関係」こそ「ソクラテスという現象」であって、自体的存在の存在を前提とするソクラテス哲学こそ西洋形而上学の起源であり、自己反省的である主観性はそれ自体倫理的性格を帯びているため、そこでは不遜にも倫理学が哲学に取って代わろうとする。しかも主観性の本性はその空白性にあり常に自足を衒うと。2016/08/22
-
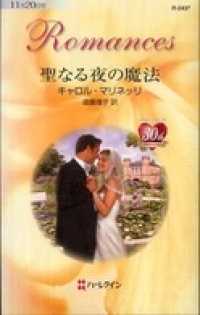
- 電子書籍
- 聖なる夜の魔法 ハーレクイン