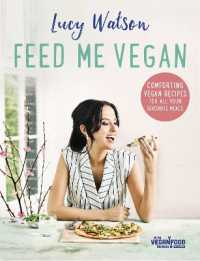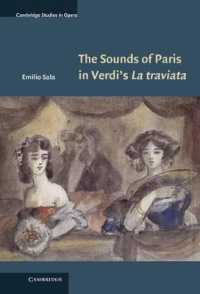- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想(近代)
内容説明
「近代の超克」議論でこれまで見過ごされてきた哲学(史)的、思想(史)的意味を問う。
目次
「世界史的立場と日本」との対比
第1部 「近代の超克」の前史(原点としての生田長江;亀井勝一郎におけるニヒリズム;中島栄次郎と保田与重郎の「不安」;保田与重郎と三木清におけるロマン主義)
第2部 「近代の超克」と「世界史的立場と日本」(二つの「哲学的人間学」―高山岩男と三木清;高山岩男『世界史の哲学』をめぐる攻防;鈴木成高における「超克すべき近代」という問題;「真剣に近代というものを通って来たか」)
第3部 「近代の超克」の行方(林房雄の「進歩性」;日本文化における「回心」;「竹内‐加藤モデル」から保田与重郎へ)
著者等紹介
菅原潤[スガワラジュン]
1963年仙台市生まれ。1996年東北大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。1998年文学博士(東北大学)。現在、長崎大学環境科学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mokohei
0
本書の議論の正しさについては判断しかねるが、知識社会学的な分析を行った著書としては今まで読んだ本の中で一番「丁寧」だと感じた。 本書の言う「再考」とは、直接的には広松渉が展開した「近代の超克」論になるだろうが、各論者の思想の検討を鍵にして、その異同を語るスタイルを徹底することで、「近代の超克」論自体を立体的に見せることに成功していると思う。2021/03/13
Erina Oka
0
漸く。2013/10/03
ポン
0
近代との対立点且つ進歩性が読みこまれるという点では、唐木順三のように戦後へと受け継がれる問題として中世文学は読まれ続けていたんだなーと感じました。10~20年代の和辻の古代回帰はどうか。2013/08/10