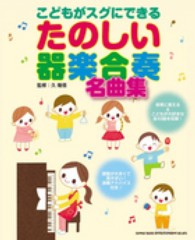目次
第1部 『試論』から『物質と記憶』まで(『試論』における「持続=心的事象」と「空間=物質」の関係;『試論』の二元論的解釈に対する疑義;『アリストテレスの場所論』における「場所」の概念;リセ・アンリ四世講義に見られる見解 ほか)
第2部 『創造的進化』とその関連著作群(『創造的進化』とその関連著作群におけるベルクソンの存在論的立場;物―心相互作用としての生命;知性的認識の生物学的起源と根本性格;知性的認識の実践的機能 ほか)
エピローグ(本書の結論;付論)
著者等紹介
本田裕志[ホンダヒロシ]
1956年東京都に生れる。1987年京都大学大学院文学研究科博士後期課程哲学専攻(倫理学専攻分科)満期(学修)退学。1998年より龍谷大学文学部助教授。2007年より同教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
雁林院溟齋居士(雁林)
0
講義録を検討しつつ、『試論』『アリストテレスの場所論』(著者はこれをベルクソン自身の哲学の展開として強調する)から『創造的進化』迄のベルクソンの存在論的立場が一貫して「修正された二元論」であったことを示している。つまり物質を精神=意識と同じ持続の緊張の度合の一展開だとする見解で、ベルクソン存在論全体の要点を纏める形になっている。当然ジャンケレヴィッチを糞味噌に貶している。又物質の直観について、それが純粋知覚や想像力であることを否定した上で実証主義的形而上学の共同作業的方法と同定していることが示唆的だった。2013/03/17




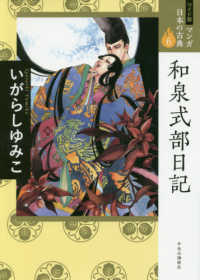
![きせかえマグネットBOXおしゃれガールズクローゼット [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44153/4415315836.jpg)