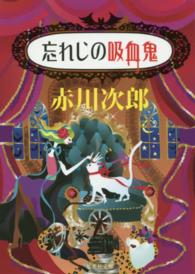内容説明
歴史研究者に大切なのは、史料を疑って読む。1つの事件の理解にも疑いをもつ。つまりは歴史に違和感をもつ、ということです。その上で、小さな違和感を拾い集め、定説に立ち向かう。それが新しい歴史理解を生む一歩となる。本書では、そうした試みを書いてみました。(「文庫版のまえがき」より)
目次
第1章 江戸時代に鎖国はなかったのか
第2章 2代将軍が天皇に激怒の「違和感」
第3章 信長の「天下」とは京都周辺だけか
第4章 なぜ西郷どんは大隈重信を嫌うのか
第5章 「男と女」の立ち位置の行方
第6章 天皇をめぐる歴史の謎
第7章 夏目漱石のワケありな門人たち
第8章 人物を語らない歴史研究でいいのか
著者等紹介
本郷和人[ホンゴウカズト]
東京大学史料編纂所教授。1960年、東京都生まれ。東京大学文学部、同大学院で石井進氏、五味文彦氏に師事し日本中世史を学ぶ。専門は中世政治史、古文書学。博士(文学)。史料編纂所では『大日本史料第五編』の編纂を担当。2016年、『現代語訳吾妻鏡』(全17冊、吉川弘文館)で第70回毎日出版文化賞(企画部門)を五味氏らと受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yamatoshiuruhashi
50
本郷和人さんという人はしっかりと彼方此方で見かける人なので歴史界の中心を行っているひとかと思ったら、ご本人の認識ではそうでもないらしい。その本郷さんが、最近の変わりつつある学説や通説に疑問を呈して解説をつける。面白い。最近の池上彰の番組でも「鎖国はなかった」なんて言っていたが、この問題も明快に解いて反駁。何せ文化系の議論はそれぞれの論拠が別にあり一つの答えは出にくいのだろうが、本郷さんの「違和感」は多くの日本人の「違和感」だろう。2024/06/07
Galilei
8
歴史の新説や余談やらで、まるで教授がゼミの休憩時間に逸話を並べた脱線みたいで肩が凝らず楽しめます。明治学院を設立したヘボン式ローマ字の発明者J.C.ヘボン(発音ヘップバーン)と女優キャサリン・ヘップバーンは一族と。本編スタイルで余談を加えると、キャサリン主演映画「旅情」のベニスは17世紀に文字と字間の小さいイタリック体の発明で、今日の単行本サイズまで出版物を小さくして欧州の1/4のシェアを誇った。▽本編の日本史は時代も人物も点でバラバラだが、歴史は従前の形而より人物が重要との一貫した主張に全く同感です。 2024/06/16
アトム
2
違和感。 この本を読み、自分は子どもの頃、歴史が好きだったと思い出した。2025/04/04
-
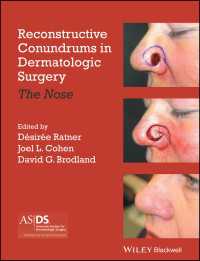
- 洋書電子書籍
- Reconstructive Conu…
-

- 和書
- 魚類の社会行動 〈3〉