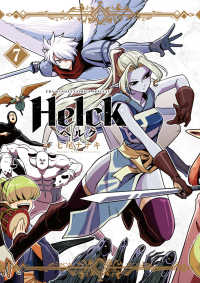内容説明
日本の武装集団を支配する特異な倫理。巨大組織を円滑に運営する、その人的構成を解明する。一般社会では理解しにくい陸軍―階級があり、命令と服従は絶対である。しかし、同じ大佐でも、中央官衙の課長と田舎の連隊長では、人の見る目が違ってくる社会である。
目次
第1章 地域閥から選択意志による「派」へ
第2章 幼年学校という存在
第3章 陸士の期、原隊、兵科閥
第4章 天保銭組と無天組
第5章 中央三官衙の緊張関係
第6章 国軍を巡る門閥と閨閥
第7章 部外者の介入
著者等紹介
藤井非三四[フジイヒサシ]
軍事史研究家。1950年、神奈川県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。国士舘大学大学院政治学研究科修士課程修了(朝鮮現代史専攻)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
CTC
13
5月の光人社NF文庫新刊書き下ろし。著者は市井の軍事史研究家だが、出身都道府県別に編んだ二巻多段組400頁の大著『陸軍軍人列伝』の作者。私にとっては頭を殴られたような衝撃の1冊。 非常に複雑と思える大組織の派閥・人事を、出身や経歴、兵科、閨閥、或いは外的要因によるもの、などに分類して理知的に語るのである。さらに序章は「辻政信はなぜ生き延びたのか」、終章は石原莞爾はなぜ挫折したのか」とくる、掴みも余韻も完璧である。 客観性を担保するものがどれほどか判断が付かぬため、やや割引くとしても、文句なしの1冊だ。2018/06/13
toriarii
2
学歴、出身、兵科、身分、姻戚、部外者のそれぞれが陸軍内部での立身出世に影響を及ぼしたのが良くわかる。巷間に言われるほど、日本陸軍の組織は非効率かつ無能ではなかったが、適切な才能を適切な場所に送り込むということにしばしば失敗した。組織の流れと、ルールを理解し上手くやりくりできるものだけが中枢で権力を振るうことができるのだろう。社会で経験を積めば積むほど本書の面白さは良くわかると思う。2018/10/07
てっき
2
人の繫がり、というものが組織にどのように影響するか、をまとめた一冊。この手の内容は他の著作でもあるが、出身地域や兵科というグループでの切り口で非常に読みやすい一冊。序章と終章が辻と石原に特化した記載となっており、そこだけなら初心者にも読みやすく、とっつきやすい内容かと思います。2018/07/15
なのは
1
石原莞爾『満州事変は仙台陸幼の作品』幼年学校でつくられた人脈による派閥、陸大 VS 陸士(たたき上げ VS 中学組)、連隊による派閥、勤続年数による上下関係、そして兵科による派閥、と建前である上意下達の指揮系統が交差しながら並存しているところに、当時の陸軍の恐ろしさを実感。軍事的才能や政略的才能よりも、まずこの複雑怪奇な派閥の海を泳いで渡るだけの幸運チートと人脈チートが何よりもものを言う世界だったのだなと。山本七平の日本軍三部作が地べたから見た陸軍ならこちらは俯瞰して見たシステムとしての陸軍2018/11/09