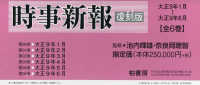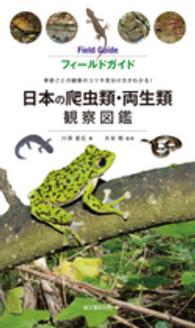内容説明
「日本兵は世界一強く、日本の戦争指導者は世界一愚かだった」米戦史家ロバート・レッキー―真の敗因、真の戦犯は敗戦によって深い闇のなかに葬り去られてしまった!勝てる戦争だったと知るだけで、半世紀前の歴史を見る目が、がらりと変わってくる。新しい指導者となる現代人のための新しい戦争史観入門。
目次
序章 大東亜・太平洋戦争は日本が勝てる戦争だった
第1章 闇に葬られた背信の戦争
第2章 「西方攻略」という勝利の戦略を捨てた謎
第3章 日本が勝てる戦争に負けた理由
第4章 敗戦の原因をつくった海軍の暗部
第5章 謀略と裏切りに翻弄された日本軍
第6章 現在にまでつづく「負けいくさ」の構造
第7章 第二次大戦は汚い謀略戦だった
終章 戦争上手という文化があった
著者等紹介
新野哲也[ニイノテツヤ]
1945年、北海道小樽生まれ。明治大学政経学部卒業。月刊「グローバル・アイ」編集長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とくけんちょ
54
薄めの本だが、中身の濃さはなかなかのもの。熱い思いが伝わってくる。日本人として自虐史観からの脱却や誇りを取り戻そう本。内容は、繰り返しが多かったり、盛り込みすぎな感もあり、読み応え?がある。日本の宣戦布告がなぜ遅れたのかなどと当たり前に流していた部分に疑問を持つことができたのは収穫。2021/07/01
ぺぱごじら
11
「ポジショントーク」とはこういうものか、と実感する一冊(笑)。何がなんでも「日本は参謀団が下手すぎた」という話にしてしまうのはまだしも、それを現代日本の経済低迷にまで繋げてしまうのは…(笑)。戦略の失敗は戦術では補えないというのは基本なので、その点について反論はないけど、今の会社組織は、その戦略的失敗を上下なく議論しようと思えば出来ることもあるし、そうなれば「有能だが物言わぬ兵士」にも責任の一端はあるのも事実だと感じる。…という意見が言える今の世の中をまず愛するべきだと感じます。2017-1002017/06/13
カズオ・ハラグロ
7
本書は論理的欠如が多くみられ、筆者の独断的な判断が多い部分が散見される。日本が太平洋戦争に負けた原因は国・軍の学歴エリート化並びに西方(ビルマ等)攻略(状況を見て、対ソ開戦)に軸を置かなかったこととしている。確かに、軍事指導力の衰え並びにミッドウェーでの暗号戦以外での敗因は史実なら同意できる。 しかし、当時の日本の財力は特に弱く、国民も大きく疲弊していたに違いない。さらに、慢性的な資源不足もある。西方攻略により、どれほどの資源を得れたかというデータを記載していない時点で論理的根拠に欠けるのは明らかだ。2018/02/01
西澤 隆
3
戦争はある意味「戦略を考えてもその通りにならずに歯がみする」もの。失敗したプランを後世で批判しながら「こうすればよかったのに」と言っていても、選んだ別のプランにだっていろんな問題は出てくるのは当たり前。日本がWW2で手を広げすぎたという点にはなんの異論もないけれど「うまくやれば勝てたものを戦略が悪いから負けた」と言っているクセに「~のはず」的な個人的決めつけが多用されていて、なんだかある種の仮想戦記ものを読むような感じ。自らの無謬を疑わずする批判は、批判している対象と同じ穴の狢。と学会に推薦だな(苦笑)。2016/02/21
Terry Knoll
2
大東亜戦争で、日本軍は優れた兵を持っていながら、愚かな指揮官による無謀な作戦のために破れた。と著者のぼやき嘆きが聞こえる。 士官学校の成績だけで昇進がきまり、失敗しても辞職更迭はなく、後日別の戦いで同じような失敗をする。 これでは死んだ兵隊は酬われません。 陸海軍は予算の分捕り合戦でいがみ合い、内部では統制派・皇道派(陸)艦隊派・条約派(海)とわかれ内ゲバ。 統合作戦などは無理。 政治家・軍人ともどのように終結させるのかまったく考えていなかった。 どのような経緯で、内部派閥ができたのかよくわかる 2014/01/21
-
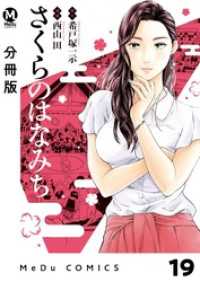
- 電子書籍
- 【分冊版】さくらのはなみち 19 Me…
-
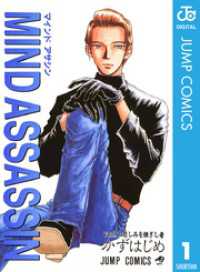
- 電子書籍
- MIND ASSASSIN 1 ジャン…