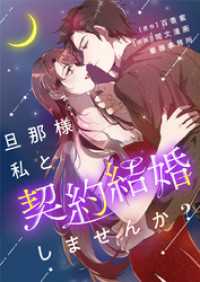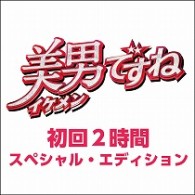内容説明
第二次大戦中の最優秀戦闘機と謳われたP51ムスタングを翻弄し、その恐るべき性能を知らしめたキ84疾風―日本陸軍戦闘機の系譜をうけつぎ、その技術を結実させた傑作機の全貌と戦いぶりを描く。陸軍戦闘機づくりに情熱をもやした中島飛行機技術陣の苦闘と名重戦誕生までの道のりを、写真と図版で徹底研究する。
目次
1 P51を手玉にとった戦闘機
2 戦闘機にかける中島の情熱
3 九一戦、華々しくデビュー
4 九七戦で地盤を築く
5 軽戦九七と「隼」の限界
6 重戦「鍾馗」の開発に着手
7 大東亜決戦機「疾風」誕生
8 四式戦隊出撃す!
9 名戦闘機の評価は消えず
著者等紹介
鈴木五郎[スズキゴロウ]
1924年7月13日、京都府中舞鶴生まれ。1943年6月、大日本飛行協会横浜飛行訓練所(学生航空連盟)で水上機の操縦訓練を受ける。1944年8月、三重海軍航空隊2期飛行予備生徒隊に入隊。1948年9月、東京大学文学部卒業。その後小学館児童編集部を経て読売新聞社出版局に勤務。1979年、定年退職。現在、航空史研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひらけん
12
本の最後に疾風の精神は脈々と受け継がれている。この文が印象的でした。中島飛行機は戦後、富士重工と名前を変えて零戦の技術を生かして作ったスバル360を始め、疾風のエンジンを設計した技術者がスカイラインを作り、トヨタのカローラを設計したのも元航空技術者。小惑星イトカワの名前の由来となった日本の宇宙開発の父と呼ばれた糸川博士も元中島飛行機の技術者。中島和久平の飛行機に熱い情熱をかけた想いを沢山の技術者がその意志を継ぎ、戦後、日本の工業の礎を築き、その確かな技術は今も脈々と受け継がれている。そこに感銘を受けます。2018/03/21
どすきん
2
表題と異なり、ほぼ、設計・製造した中島飛行機の話に終始するが、昭和18年12月、実戦投入から2年半くらい経過するまで国民に存在自体が知られていなかった零戦が、旧帝国陸海軍を代表する戦闘機の様に扱われる中、初期の段階から映画「加藤隼戦闘隊」が作られていたりして隠す気なしの陸軍機が、意外に知られていない理由が分かった気がする。2016/04/14
Tomotaka Nakamura
0
疾風の本というより中島飛行機製作所の歴史と言った本。最近のノンンフィクションに多い、ライバルをおとしめて主役を高める体裁の本。凄さを表現する手法としてはやはりあまり好きではない。中島飛行機自体は好き!2014/04/09
U-G.Kintoki
0
兵器の開発史は面白い。悲壮に描かれることが多い大戦末期にあって、割とポジティブな書き方になってた。品質面は当時の日本の工業力全体の問題でもあるしある程度仕方ないにしても、せめて集中運用できてればな~。2013/06/01