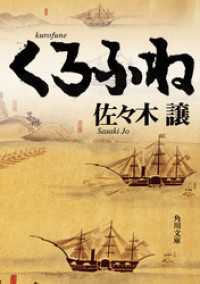内容説明
昭和二十三年八月二日、復員―思えば赤紙召集により故郷を出て以来、八年目。中国の戦野を駆け巡り、行きついた先はシベリヤだった―凍土にしがみついて黒パン一日三百五十グラムの粗食に耐え、厳しいノルマを果たした日本将兵たち。底抜けの陽気と陰気が、いつも同居する不思議な国・ソ連での抑留生活を綴る。
目次
戦利品の山
西から昇る太陽
シベリヤのコヤシ
ソ連と中国の少年
ラーゲリ到着
第十二ラーゲリ
銃弾の明治節
天突き体操
松ボックリ
最初の逃亡〔ほか〕
著者等紹介
斎藤邦雄[サイトウクニオ]
大正9年11月、群馬県藤岡市に生まれる。昭和16年3月、東宝在職中に召集により、高崎東部38部隊第1機関銃中隊に入隊。一期教育終了後の7月、北支「陣」部隊(河北省)へ転属。20年6月、部隊は満州へ移動し、関東軍の指揮下に入る。同年10月、シベリヤへ抑留となって、イルクーツク地区の四カ所のラーゲリを転々とする。23年7月、復員。東宝を退社してフリーとなり、「東京児童漫画会」に所属し、各児童雑誌に執筆する。40年、フジテレビエンタプライズに入社、TVアニメの制作を担当する。48年に退社(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
糜竺(びじく)
40
シベリア抑留に興味を持ち、どんなものなのか知りたくなり購入しました。本当はとても辛い体験であったはずなのに、著者の人柄なのか、あまり暗さは感じられず、いがいに面白くとても興味深く読めました。読んでいると、本当にそんな事がありえるのか、と考えてしまうような色んな体験が散りばめられていました。著者のイラストも載せられていて、それもいい感じで本の中身を引き立てていました。やはり、話の終盤の、日本へ帰る頃の出来事は、読んでいて感情移入してしまい、少し泣きそうになってしまいました。オススメの本です。2015/08/02
さいちゃん
17
実は父に頼まれて買った本を、先に読んじゃいました。「シベリヤ抑留」、聞いた事はあるものの、詳しくはわからず、どんな事だったのか、今回わかったように思います。本書はどこか面白おかしく書いてますが、やはり泣ける部分もあり、一人一人の必死さが伝わりました。戦争が終わっても、引き続き、別の意味で戦争をしてた人達がたくさんいたんですね。2015/08/15
CTC
9
06年光人社NF文庫、単行本は88年同社。先に読んだ『陸軍歩兵よもやま物語』は、ある中国系サイトに40万部売れたとの表記があったが、故にか続編である。ふんだんな挿絵が却って門外漢に取り付くシマを与えないのではと思うが、軽い読み口での抑留体験談は貴重である。ひと口にシベリア抑留といっても57.5万人(異説あり〜70万人)が70箇所以上の収容所に留置されて、その処遇も様々だからなんとも申せないが、特に軍歴の浅い若い兵の中には抑留中「兵隊より捕虜のほうがいい」と話す者も多かった(初年兵虐待が酷かった)という。2020/05/06
Yotsuba
8
私の祖父もシベリア抑留兵でした。もっと色々聞いとくべきだったなと後悔。聞いた話はジャガイモの皮剥きの話くらい。本書は思わず、くすっと笑ってしまうシーンや、うるっとするシーンもあり、挿し絵付きの軽快な文章で書かれています。だけど決して楽ではなく苛酷な労働の毎日。生きて帰ってきてくれた祖父に改めて感謝。2015/08/15
もちもち
5
重いテーマの本だが、新聞4コマを彷彿とさせる暖かいタッチのイラストが挿入されているのでどこかほのぼののしたものを感じる。 シベリア抑留ものって必ずお人好しなソ連人が出てくるが、何割かはお人好しな人がいる国民性なんかな?2021/09/06