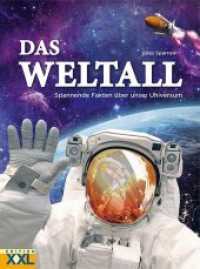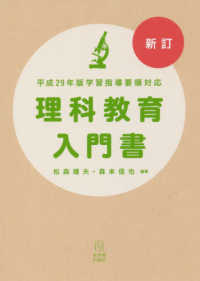内容説明
明治五年、天皇の身辺を警護する御親兵は「近衛兵」と名を改め、陸軍大将西郷隆盛がその都督となる―帝国陸軍は、創設以来、国民の信頼の中で成長し、国の強弱の尺度となり、また、国の発展の礎となって明治・揺籃期を駆けぬけた。列強重囲の中で、清国とロシアを相手に戦捷を果たした陸軍の指導統帥を描く。
目次
第1章 明治建軍
第2章 日韓および日清談判
第3章 成歓と平壌の戦闘
第4章 日清戦争の勝利
第5章 戦勝の後に三国干渉
第6章 聖戦、日露戦争
第7章 大山、児玉、黒木
第8章 遼陽戦と弓張嶺夜襲
第9章 日本の誉れ・太子河作戦
第10章 旅順要塞の死闘
第11章 沙河および奉天会戦
第12章 軍閥国に尽くす
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
筑紫の國造
3
おそらく軍事記者としては日本でも5指に入るであろう伊藤正徳による、「近代日本陸軍史」。伊藤は海軍記者だが、本書は陸軍が主役。第1巻は建軍から日露戦争終結まで。「現代の軍記物語」とでも呼ぶべき名調子は健在で、情景描写や巧みな比喩、流れるような文体は無二の感がある。「軍閥」といえば悪いイメージがあるが、本書では本来の単に「軍部」を指す言葉として使われる。著者曰く、日露戦争までの軍閥は統制がゆき届き、政治に介入せず、大局観を持った指導者によって国家に貢献する所大であった、と。2016/06/05
くらーく
2
山縣、大山、児玉が中心で話が進んでいく。どうして、明治時代は政治と軍事がうまく調和して、二つの戦争を勝てたのかが、よく分かるな。軍が政治に首を突っ込まなかったのは何故だろうか。自制が効いている。 明治維新体験者だからかなあ。明治人の人格形成と昭和人の人格形成と何が異なったのだろうか。幼年から純粋培養したせいかねえ。本に答えが書いてあるわけではないけれど。2018/03/10