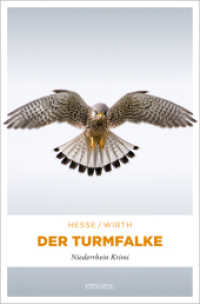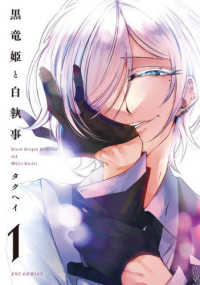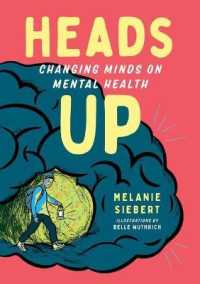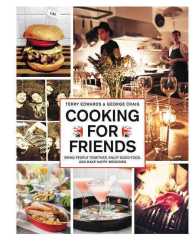内容説明
油の供給の豊富なる国は光り栄え、油のなき国は自然に消滅す―。南方に徴用された石油技術者七千人、密林ふかく分け入り、石油を採掘精製して日本へ還送し、太平洋戦争を支えた石油戦士たちの知られざる戦い。石油獲得を企図として実施されたパレンバン落下傘部隊“空の神兵たち”の活躍とともに描く話題作。
目次
第1章 南十字星の下へ
第2章 戦争か屈伏か
第3章 艱難辛苦の末に
第4章 石油戦の尖兵
第5章 神話の崩壊
第6章 天国と地獄
第7章 苦難の道のり
第8章 焦土の中から
著者等紹介
石井正紀[イシイマサミチ]
昭和12年、東京品川に生まれる。早稲田大学第一理工学部建築学科卒業。千代田化工建設(株)、千代田テクノエース(株)を経て、現在、石井正紀技術士事務所を主宰。在社中は主としてプラントの建設に従事し、エクアドル、サウジアラビア、アルジェリアに長期滞在する。現在もウズベキスタンの鉄骨橋梁会社の技術指導のため、同国との間を往き来している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
94
間もなく12月8日、80年目の開戦記念日。日本が何故、米英との戦争に突入したか、改めて議論があるであろう。いずれにせよ南部仏印進駐を受けた米国による石油の全面禁輸措置が一因に違いない。戦争遂行には南方(蘭領東印度)の石油資源の確保が必須と考えられた。このため開戦後、間もなくスマトラ島パレンバンにある二つの製油所と背後にある油田地帯を、出来るだけ敵に施設破壊の暇を与えぬよう、陸軍落下傘部隊により急襲制圧。時を移さず民間から徴用された石油技術者集団が海路進出。製油所や油井の復旧に奮闘、操業再開にあたった。 2021/12/05
rico
84
「白紙」(しらがみ)って初めて知った。徴用令状とでもいおうか。軍艦も飛行機も石油なしには動かせない。その石油の確保のために、「白紙」1枚で南方に送られた技術者たち。現地での彼らの奮闘ぶりや軍人との対立、多くの犠牲者と。そもそもそんなに重要な石油の埋蔵量が1:300というアメリカとまともにぶつかれば勝ち目がないことがある程度共有されていたのにもかかわらず、どうして・・・とまた思う。読みやすいものではない。でも、大学卒業後技術将校として石油採掘のため南方に行った父を持つ私は、読まなければならないと思った。2021/09/03
kaoru
69
アメリカの対日石油禁輸に対抗してスマトラのパレンバン油田に赴いた日本人技術者達の苦闘を描く1冊。生命線たる石油を獲得するべく、軍部は落下傘部隊を投入して蘭印から二つの製油所を奪った。石油技術者達の尽力で製油所は航空燃料の生産に成功し現地は束の間の繁栄を享受するも、数年後に連合国の空襲を受けて敗走する。国家総動員法で徴用された石油技術者達の真摯な努力、軍部の硬直ぶり、陸軍と海軍の軋轢など戦争の諸相が理解でき、国家にとっての石油の重要性を再認識した。学徒動員でスマトラに赴きパレンバン大空襲を経験したという→2023/02/17
TATA
30
戦時中に蘭印のパレンバンに赴くことになった石油関連技術者たち。本土よりは恵まれた生活とはいえ徐々に戦火は避けられないものとなっていく。戦争を語る書籍は数多あるわけですが、その中でも視点の少し異なることで読み応えのある作品でした。ただ、どうしても辛い描写はあるわけですが。2023/10/14
dongame6
7
太平洋戦争におけるインドネシア、パレンバン油田を巡る石油獲得作戦を、主に民間技術者の視点から描いた本。著者が(たぶん)石油関係の仕事をしている人だけあって、一般的でない石油の作井や精油についてもよく描かれているように思う。開戦前の「人」の確保から、有名な落下傘降下作戦、占領後の油田の復旧作業や、復旧後の石油を巡る陸海軍の確執、軍人の徴員差別、タンカー問題と1944年以降の航路途絶後の油田地帯の様子など、他の戦記物ではちょっと見られない事が多く、非常に面白い。また、戦後、復員するまでの苦労譚も興味深かった。2012/08/29