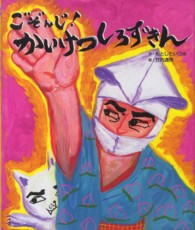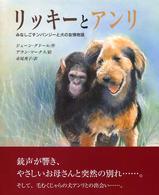内容説明
世界を驚嘆させた“真珠湾攻撃”以後、洋上作戦の主役として君臨し、戦争の様相を一変させた空母―世界最初の空母「鳳翔」以来、高度な日本の造艦技術と海軍の伝統が生みだした数多くの名艦のすべてを、米英の空母の歩みとともに徹底的に解剖し、その波乱の軌跡をたどるファン必携の一冊。写真図版百五十点。
目次
プロローグ 空母の誕生
第1章 実験空母「鳳翔」の成功
第2章 条約型空母「赤城」「加賀」
第3章 理想的な中型空母の誕生
第4章 艦隊型の大型空母「翔鶴」型
第5章 近代空母の極致「大鳳」
第6章 急造の中型空母「雲龍」型
第7章 まぼろしの超空母「信濃」
第8章 機動部隊を支えた補助空母
エピローグ 戦後の空母
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
13
メインは日本艦ながら、原子力空母エンタープライズまでの世界の空母の歴史がコンパクトに詰まっていていかにも「入門」らしい入門書。日本海軍と言えば大艦巨砲主義のイメージだが、当初、他の艦からの実験的改装がメインだった空母界に、颯爽と世界初の純正空母として躍り出たのが日本の鳳翔であり、空母史においてもその技術力を見せつけていたことがよくわかる。鳳翔はその後、練習艦として活躍したことも含めて、まさに空母の母と言って過言ではない。水上機母艦や航空戦艦と空母の違いなどかなり基礎的なことからわかる2014/05/06
NICK
5
人間は文明を手に入れてから、陸は言うまでもなく、海を渡る技術を編み出し行動領域を拡大してきた。陸海を征く技術が何千年という歴史を持つのに対し、人間が「空」を獲得したのはライト兄弟以降のことで、わずか一世紀にすぎない。ライト兄弟の初飛行からそれほど間を置かず、飛行機の軍事転用というアイディアが現れたのは驚きである。「空」の歴史は非常に短いのにも関わらず、航空機、またそれを運用する航空母艦が海戦の主役となり、戦艦に代わり国防の要を務めるようになったというのは戦争とテクノロジーの相互作用を改めて思い知らされる。2014/08/11
おっくー
4
戦艦入門の続きで買った本。歴史上新しい艦種である空母についてわかりやすく解説している。日本の建造技術がすごい。2014/08/01
好古
3
【雑記】戦艦は12隻でそれぞれ個性もあって特徴も名前もわかりやすいが、空母となると形は似たり寄ったりで名前も飛龍、飛鷹、瑞鶴、瑞鳳と一字違いで数も多く覚えずらい…と思いこの本を買ってふむふむなるほどわかりやすいなと思って読了し読メに登録したら4か月前に読了とある…。1年ならまだしも半年も経たないのにこんなことがあっていいのだろうか…。正直若干の既視感はあったものの、多くの軍事書籍を読んでいるので多分似たような文章があったのだろうとそこまで気にかけなかった。我ながら絶句。因みに同じ本を二度買うのは二度目…。2024/12/13
好古
2
【備忘】①加賀は改装前、煙突が艦尾まで伸びておりそれにより隣接の准士官室が40度に達した。(まるでセントラルヒーティングだ)②飛龍と赤城は右舷の煙突の熱気と左舷の艦橋が起こす気流で乱気流が起こった。③翔鶴は蒼龍の拡大改造型。日本空母は蒼龍を基礎に発展していった。④米国はエセックス級を23隻建造したが日本は翔鶴級を2隻しか作れなかった。⑤米国は珊瑚海海戦の戦訓に則り炭酸ガスによる消火でヨークタウンを火災から救った。(その後沈没)⑥煙突の熱気問題は煙突を傾斜させることで解決された。信濃、隼鷹、大鳳など。2024/08/26
-
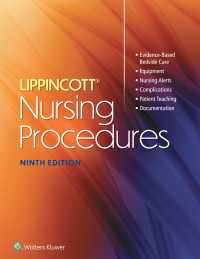
- 洋書電子書籍
- Lippincott Nursing …