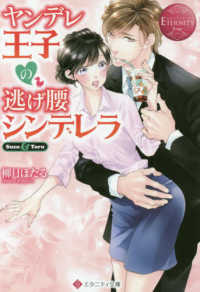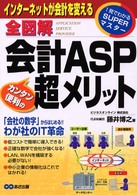内容説明
民主主義はやっかいだけど、時間をかけてこだわって、ていねいに、がまんしつつも面白く。おいしいコーヒーを味わうために、豆の栽培や輸入法、焙煎や淹れ方にも気を配り、時間をかけるように。第一線の政治記者がしばし永田町を離れ「草の根民主主義」が脈打つ現場を歩く!
目次
プロローグ インドネシア・スラウェシ島のカフェで民主主義を紡ぐ
第1章 ポートランド―対話をあきらめない街(DIYが息づく街―まずは自分が動き出す;街づくりを楽しむポートランドの人々 ほか)
第2章 日本でも芽吹く「政治を語る場」―最初の一歩を踏み出した若者たち(頑張れ女の子―世界を変えるのも、救うのも;少年院を出て―この春、再出発するあなたへ ほか)
第3章 中国と韓国の社会的企業―接近するビジネスと公益(スピードで変化を実現―中国の課題解決に社会的企業ブーム;個人の体験が進歩を後押し―中国テクノロジー、日進月歩の原動力 ほか)
エピローグ フランスの若者は、なぜデモに参加するのか?
著者等紹介
秋山訓子[アキヤマノリコ]
1968年東京生まれ。東京大学文学部卒業。ロンドン政治経済学院修士。朝日新聞編集委員。朝日新聞入社後、政治部、経済部、『AERA』編集部などを経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
49
まさに、タイトルにあるとおり、政治・民主主義は日常の生活の中にあるはずなのだ。が、この国は、その逆を行っているし、そう仕向けられているのかとも思う。現状維持は後退であるのことは、言うまでもない。そんな現状の中でも、小さな変化を起こそうとすることができる。まずは、そこからだ。小さな変化を、諦めずに繰り返すこと。2024/01/15
ヒデミン@もも
48
秋山さんの文章はしなやかで柔らかい。ジェンダー、人権などの社会問題や政治を語っていてもわかりやすい。まずは、身近な問題解決から。2021/01/07
spatz
16
著者は政治担当の記者さん。記事をまとめ直したもの、冒頭のポートランドの話のインパクトはやはりアメリカという移民の多い国だからこそなのか。ていねいに。じかんをかけて、こだわって。我慢しつつも面白く。おいしいコーヒーをいれるのとおなじように。コーヒーの比喩はカフェが人々の集まる所になる取材がいくつかあったから。人々の手の届く所に、自分たちがかかわる形で。政治とはそんなもの。この本、紹介してくれてありがとうございました😀2021/04/24
かじ
9
著者が出会った彼、彼女たちにとって「政治」は特別なものではない。3年、4年に一度考えるものではなく、人々の暮らしに“当たり前にあるもの”である。学校や職場、地域やコミュニティなど、それぞれにとっての日常生活の中に「民主主義」が息づいている世界には、活き活きとした個人があり、パワーが宿っている。諦めや抑圧に馴れてしまった鬱々とした現代社会にこそ必要なのは、カリスマ的な指導者や全体主義ではなく、私たち一人ひとりなんだと改めて認識させられる著書である。2021/04/02
naolynne
2
本来、政治は生活と身近なもの、身近であるべきもの。朝日新聞政治記者の著者は、政治に関心を持てない人、自分にはどうにもできない世界と諦める人にそれでいいのと問いかけている。2022/01/25