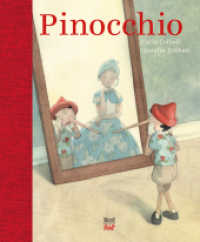目次
1 民主主義と死刑制度(自分の子どもが殺されても死刑を求めないのか;何が死刑をタブーにしているのか ほか)
2 オウム事件と公安(震災とオウム真理教事件、激動の一九九五年;オウム真理教事件と公安警察 ほか)
3 日本の刑事司法(オウムで生き延びた公安調査庁;刑事司法に隠された麻原彰晃 ほか)
4 朝鮮半島、沖縄、日本の敗戦後(北朝鮮を取材することの難しさ;拉致問題は日朝関係を変えたか ほか)
5 メディアの闇(タブーを生む“標識”;真実をねじ曲げるタブー ほか)
著者等紹介
森達也[モリタツヤ]
1956年、広島県呉市生まれ。映画監督、作家。明治大学情報コミュニケーション学部特任教授。98年、ドキュメンタリー映画「A」を公開、ベルリン映画祭に正式招待。「A2」では山形国際ドキュメンタリー映画祭で特別賞・市民賞を受賞。2011年、『A3』(集英社インターナショナル)で講談社ノンフィクション賞受賞
青木理[アオキオサム]
1966年、長野県生まれ。ジャーナリスト、ノンフィクション作家。慶應義塾大学卒業後、共同通信に入社。社会部、外信部、ソウル特派員などを経て、2006年に退社しフリーに。テレビ・ラジオのコメンテーターなども務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
matsu04
27
警視庁公安部によるオウム捜査の実情について、青木氏が詳細に調べていることがよく分かる。日朝関係や拉致問題についても然りだ。こうした経験と分析に基づく氏の主張は傾聴に値する。死刑制度に関する考察(私見とは異なるものの)も考えさせられる。2016/02/18
makimakimasa
9
死刑の現場の密行主義、法的根拠の無い囚人との接触制限、情報公開を求めないメディア、無知なのに死刑賛成の社会。オウム事件を教訓にするなら特異性だけでなく普遍性にも目を向けるべき、麻原を信者の裁判の証人に呼ばない矛盾、それに沈黙するメディア。組織に入ると何かが停止する個人、企業論理に優先されないジャーナリズム、結果バッシングを恐れ思考停止するメディア、遺族の感情に配慮して隠される遺体映像や加害者の手記。青木氏の発言は「クソのような嫌韓論者」とか「アメリカの尻の穴を舐めてるだけ」とか、時折やや感情的で品が無い。2022/03/16
こすもす
6
こういう本を読むと何を信じたらいいのかわからなくなる。逆に何でも疑ってかかるのがいい のかもしれない。 2017/11/23
Gen Kato
5
「物議を醸すからジャーナリズムなんです。ところがこの国の新聞社やテレビ局などは大企業になっちゃった」「誰だってトラブルは避けたい。まして組織は一般的にトラブルをマイナス点とみなします。そしてそこから逃避し、ルーティーンという日常に埋もれていれば、そこそこは忙しい」「一気呵成に遺族の心情を理由にしてバッシングする。しかも本音は自分が見たくない」「マスゴミなんていう言い方でメディアを十把ひとからげにして一刀両断にするのは、単なる思考停止」…頷かされるところが多かった。2020/01/21
竹
3
図書館で森達也氏の著書を探す中、青木理氏との対談ということで、借りた。両氏のものの見方には共感できるところが多く、勉強になる。死刑制度にしろ、オウムにしろ、刑事司法にしろ、それぞれ裏付けるだけのこれまでの経験、実績もあるだけに、説得力のある内容だった。2020/08/24