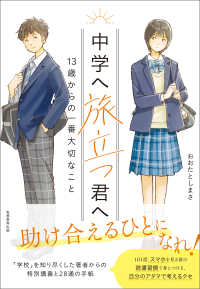出版社内容情報
ヴィオラ母さん、猫、昆虫、そして老いの先人たち……
私の生き方の原点がここにあった――
コロナ禍、母の死を経て見えてきた
ヤマザキマリ流、老いと死との向き合い方。
●寿命が何歳であろうと、その時までを思い切り生きていけばいい
・なぜ人は、老いや死に対して大きな拒絶感を抱くのか?
・なぜ人は、若さにばかり価値を置きたがるのか?
・なぜイタリア人は、新車より中古車を好むのか?
・なぜ、「何者か」にならないといけないのか?
・なぜ、イタリアは老人を敬い、日本は老害扱いするのか?
・なぜ、夕焼けは雲があるほど美しいのだろう?
・人に備わる知性、感性、命の機能を十分に使いこなすには?
幼少期から老人と触れ合い、
親の介護、そして死を経験し、
多種多様な「老いと死」に触れてきた
真の国際人・ヤマザキマリが
豊かな知見と考察をもとに語った、
明るくて楽しい、前向きな人として生き方。
■目次
1章 生きて死ぬ摂理
2章 老いの価値
3章 善く生きる
4章 私の老い支度
5章 母を見送って
■著者プロフィール
ヤマザキマリ(やまざき・まり) 漫画家・文筆家・画家。東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。比較文学研究者のイタリア人との結婚を機にエジプト、シリア、ポルトガル、アメリカなどの国々に暮らす。2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。2015 年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。著書に『スティーブ・ジョブス』(ワルター・アイザックソン原作)『プリニウス』(とり・みきと共著)『オリンピア・キュクロス』『国境のない生き方』『ヴィオラ母さん』『ムスコ物語』『歩きながら考える』『人類三千年の幸福論ニコル・クーリッジ・ルマニエールとの対話』など。
内容説明
老いの先人たち、ヴィオラ母さん、猫、昆虫…私の生き方の原点がここにあった―コロナ禍、母の死を経て見えてきた老いと死にまつわるエッセイ。
目次
第1章 生きて死ぬ摂理(延命と若返りに拘りを持つ生物、人間;死ぬこと=不吉な出来事、ではない ほか)
第2章 老いの価値(酸いも甘いも噛み分けて;老人を排除しない社会 ほか)
第3章 善く生きる(ソクラテスの「善く生きる」;表層的ではない優しさ ほか)
第4章 私の老い支度(ありのままの自分を許す;息子への伝言 ほか)
第5章 母を見送って(母リョウコの逝去;魂と肉体 ほか)
著者等紹介
ヤマザキマリ[ヤマザキマリ]
漫画家・文筆家・画家。東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。比較文学研究者のイタリア人との結婚を機にエジプト、シリア、ポルトガル、アメリカなどの国々に暮らす。2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
キムチ
ネギっ子gen
とよぽん
いち
-
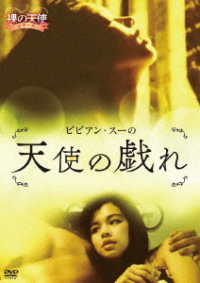
- DVD
- ビビアン・スーの天使の戯れ