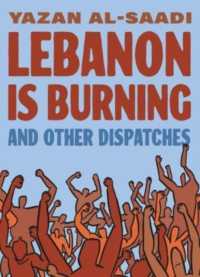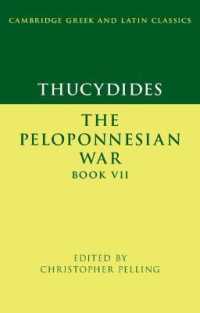内容説明
なぜ世界の親は変わったのか?結婚、出産、育児、教育。各国のデータからわかってきた新常識!
目次
第1部 不平等な時代の子育て(育児スタイルと経済学;ヘリコプター・ペアレントの出現;世界各国の育児スタイル;不平等、育児スタイル、子育ての罠)
第2部 歴史のなかの子育ての変遷(鞭からニンジンへ―専制型の子育ての終焉;男子vs女子―ジェンダーの役割の変遷;出生率と児童労働―大家族から小家族へ;子育てと階級―英国における貴族階級vs中産階級)
第3部 政策が子育てに与える影響(学校制度の組織;子育ての未来)
著者等紹介
ドゥプケ,マティアス[ドゥプケ,マティアス] [Doepke,Matthias]
西ドイツのハノーファー出身。ノースウェスタン大学経済学教授。2000年にシカゴ大学でPh.D.(Economics)専門は経済成長論、開発経済学、政治経済学、家族の経済学、人口経済学。アメリカ人の妻マリサとの間に3人の息子がいる
ジリボッティ,ファブリツィオ[ジリボッティ,ファブリツィオ] [Zilibotti,Fabrizio]
イタリアのエミリア・ロマーニャ出身。イェール大学国際経済学・開発経済学Tuntex教授。1994年にLSEでPh.D.(Economics)専門は開発経済学、マクロ経済学、政治経済学、中国の経済発展。スペイン人のマリアとの間に1人の娘がいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
25
研究内容は荒削りながら、着眼点の鋭さと個性がある一冊。本書のテーマは『経済状況が子供への教育方法をどのように変えるか』というもの。人間自体はそれほど変わらないのに教育の仕方が変わっていくのはなぜかという素朴な疑問に経済の観点からアプローチしており、興味深い話が多い。意外に勤勉さを重要視すると格差が開いていくというのはなんだか面白い(ただし、アンケート数が十分かということや勤勉という表現が各国で一致しているのかという問題点がある)。教育方法を三つのタイプ(専制、指導、迎合)に分けているのも特徴的。2022/07/06
りょうみや
22
経済学者が書いた教育・育児の分析本。単にお金の面だけでなく広い意味での人間の行動選択を扱う。いわゆる経済学的思考の本としてもわかりやすい。どんな国・時代・文化でも親は子の幸せのために利他的に育児をしていることを前提として、親の持つ資源(資金、時間、知識)の制約と、置かれた環境(格差の大きさ、社会の流動性、教育のリターン)の中で、子が将来の社会で生きていけるために最適と思える育児スタイルを選択してきたというもの。各国、各時代の教育スタイルの具体的分析もある。2021/03/03
hana87
12
育児を経済学の観点から見つめ直す1冊。統計・分析解説多めで”学術書”感があるのですが、なんとか乗り越えて読むべき! “どんな親になるかは、その社会の経済的インセンティブで決まる”ことを国別、文化別などいろんな切り口で分析。自分の子育てが何に制約されているのか、何が不安でこの行動をしているのか、色々客観的になれます。 続きはブログで! https://hana-87.jp/2021/03/16/love_money_parenting/2021/03/10
jackbdc
5
国際比較で日本型子育ての特長を把握できる事が意外だった。育児スタイルは社会経済の影響を受けるという仮説の上で、3タイプ①放任、②中間、③専制のスタイルを社会経済事象と比較して分析している。日本は③の割合が極めて低いというが、a)経済格差、b)税の累進性、c)教育リターンの大きさ等との回帰分析の結果が日本の傾向a)小、b)大、c)小を反映しているように見えて興味深かった。しかし疑問も沢山ある。データの正確性はいか程か?とか、家庭以外の要因(教育制度や地域社会)との関係性なども考慮に入れる必要があるだろう。2021/06/26
かわ
4
「ほどほどにできない子どもたち」で挙げられていたので、続けて読了。 経済学の視点から、日本も含めた国々でどのような教育が行われてきたかを時代を追って分析されている。 教育方針を専制、指導、迎合の3パターンに分類しているのも新鮮だった。経済学で親の愛情を語ることもできるんだ。2025/08/27
-

- 電子書籍
- わたくしのことが大嫌いな義弟が護衛騎士…
-
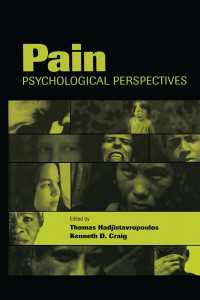
- 洋書電子書籍
-
痛み:心理学的考察
Pain :…