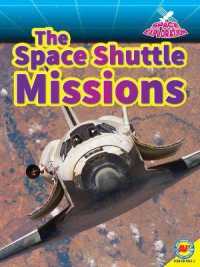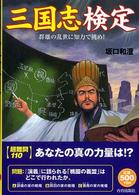出版社内容情報
「信用」を手がかりに
近代通貨の起源を探る
前近代の社会では、経済取引を円滑に進めるために、人々はどんな仕組みを編み出したのか。近代への移行によって、それはどう変化したか。
ヨーロッパで発展した「専業銀行」中心史観のレンズを外し、アジアの視点から独自の発展を遂げた「信用貨幣」の本質に迫る。
▼「歴史実証」の手法に基づき、貨幣と信用の関係を、藩札の流通や当事者の関与の仕方から捉えた画期的な作品。
▼「ヨーロッパのレンズ」を外し、インド・中国を含む、アジアの視点を加えることで見えてくる新しい信用貨幣のかたちを考察。
▼充実した執筆陣が、近世~近代、そして現代の暗号通貨に至るまでのダイナミックな変遷を、多面的に論じ浮き彫りにする。
現代の貨幣システムが形成される経緯を歴史的視点から考える。
近世から近代にかけての日本の貨幣システムの分析を縦糸とし、近代移行期のアジアの他地域における貨幣システムの変化との比較を緯糸として、信用貨幣の生成と進化について論じる。近代の金融システムの中では覆い隠されていた信用貨幣の本質を焙り出し、中央銀行と預金銀行の二層から成る現代の貨幣システムを再検討するうえで示唆を与える。
内容説明
「信用」を手がかりに近代通貨の起源を探る。前近代の社会では、経済取引を円滑に進めるために人々はどんな仕組みを編み出したのか。近代への移行によってそれはどう変化したか。ヨーロッパで発展した「専業銀行」中心史観のレンズを外し、アジアの視点から独自の発展を遂げた「信用貨幣」の本質に迫る。
目次
信用貨幣をみる視点
第1部 近世日本における貨幣と信用の展開(~幕末まで)(16世紀日本における貨幣の発行と流通―銭から三貨への移行を中心に;近世日本の紙幣―小規模藩・三日月藩を中心に;近世紙幣の流通基盤―地域内流動性不足の観点から;藩札発行における領主の機能;近世大坂米市場における価格形成の安定性)
第2部 近代移行期から現代にかけての信用貨幣の進化(アジアの視点から)(日本における近代信用貨幣への移行―国立銀行を中心に;戦前期における「預金銀行」の実態;20世紀前半期中国における地域的貨幣と信用;両大戦間期のインドにおける通貨制度と金融制度の「再編」;貨幣の形態進化と信頼の深化)
著者等紹介
鎮目雅人[シズメマサト]
早稲田大学政治経済学術院教授。1963年生まれ。85年、慶應義塾大学経済学部卒業、日本銀行入行。2006~08年、神戸大学経済経営研究所教授、日本銀行金融研究所勤務などを経て2014年より現職。博士(経済学:神戸大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
-

- 電子書籍
- 九条社長は秘書の私をお世話したい~オト…