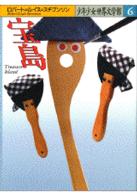出版社内容情報
外国判決承認制度を私権実現の制度であると明確に意識、その要件及び効果の側面から、比較法的手法も用いて、繊細かつ明確に解く。判決の国際的調和とは何か。
現行民事訴訟法118条は、明治23年民事訴訟法に淵源を有するが、基本的には大きな変更を受けずに現在に至っている。この条文は外国判決の承認に関する多くの論点についてどのように対処してきたのか。
市民生活が急速に国際化し、私法上の法的紛争もまた国際化が著しい現在、外国判決承認制度の目的とは何なのか、判決の国際的調和とは何か。
外国判決承認制度を私権実現の制度であると明確に意識しながら、その要件及び効果の側面から、また比較法的手法も用いながら,繊細かつ明確に解き明かす。
はしがき
Vorwort
<b>第?部 総 論</b>
<b>第1章 序論</b>
? 外国判決と国際的な法的安定性
? 本書における検討の基本的視点
――主権の調整から私権の実現にむけた制度へ
? 検討に際しての比較法上の対象
? 本書の検討対象
<b>第2章 わが国における外国判決承認制度の歴史的概観</b>
? はじめに
? テヒョー草案
? 明治23 年民事訴訟法
? 法典調査会第2部による民事訴訟法案
? 大正15年改正
? その後の展開
1 民事執行法の制定
2 平成8年民事訴訟法改正
? 本章のまとめ
<b>第?部 要件論</b>
<b>第1章 間接的一般管轄</b>
<b>第1節 外国判決承認要件としての国際裁判管轄</b>
<b>――間接管轄の基本姿勢と鏡像理論をめぐって</b>
? 問題の所在
? 比較法
1 アメリカ合衆国
2 カナダ・ケベック
3 ドイツ
? わが国における理論状況
1 学説
2 判例
? 検討
1 間接管轄の基準――判決国法か承認国法か
2 ドイツ型鏡像理論の妥当性
3 間接管轄の判断基準と直接管轄カタログ
4 最判平成10年4月28日の位置づけ
? 結び
<b>第2節 米国判決の承認と国際裁判管轄</b>
<b>――いわゆる不統一法国の間接管轄</b>
? 問題の所在
? ドイツにおける議論
1 1999年判決以前の議論
2 1999年連邦通常裁判所判決
3 判決に対する反応
? 日本法への示唆
1 わが国の学説の状況
2 裁判例
3 検討
? 結び
<b>第2章 送達</b>
<b>第1節 外国判決承認要件としての送達</b>
? 問題の所在
? ドイツ法の概観
1 適用範囲
2 応訴概念
3 要件の審理
4 送達の適式性
5 送達の適時性
6 送達の瑕疵の治癒
7 適式性と適時性の関係
8 被告の上訴提起義務
? 日本法の状況
1 総論
2 各論
? 検討
1 要件の審理
2 応訴の範囲
3 適式性と適時性
4 公示送達の扱い
5 訴状の直接郵送の問題
6 承認国法による瑕疵の治癒
7 被告の上訴提起義務の有無
? むすびにかえて
<b>第2節 渉外訴訟における付郵便送達の適法性</b>
<b>――国際送達と手続保障:第1 節の補足を兼ねて</b>
? 問題の所在
? ドイツにおける国際付郵便送達をめぐる議論
1 ドイツ連邦通常裁判所1998年判決
2 学説の動向
? わが国における議論
1 序
2 適法説
3 不適法説
? 検討
1 国際的付郵便送達の適法性
2 付郵便送達をなしうる時期
3 教示義務および判決承認
? 結語
<b>第3章 公序</b>
<b>第1節 外国判決の承認と公序</b>
<b>――名誉毀損に関する英国判決のアメリカ合衆国における承認をもとに</b>
? 問題の所在
? アメリカ合衆国における議論
1 はじめに
2 外国名誉毀損法の適用に際して公序が問題となった判例
3 外国名誉毀損判決の承認に際して公序が問題となった判例
4 判例に対する反応
5 英国名誉毀損判決を不承認とした判決の影響
6 小括
? わが国における承認要件としての公序
1 承認要件としての公序
2 公序違反が問題となる場合
3 公序と内国牽連性
? 結び
<b>第2節 懲罰的損害賠償を命ずる外国判決の承認</b>
? 問題の所在
? 懲罰的損害賠償をめぐる国内法上の議論
1 不法行為法上の議論
2 その他の法分野での議論
? 外国判決承認制度との関係
1 学説
2 判例
? 検討
1 懲罰的損害賠償制度と日本の損害賠償制度
2 反公序性の判断
<b>第3節 国際民事訴訟における判決の抵触と公序</b>
<b>――ドイツにおける議論を中心に</b>
? 問題の所在
? ドイツにおける議論
1 ドイツ民事訴訟法328条
2 ヨーロッパ民事訴訟法
3 その他の条約
4 小括
? 日本における議論
1 判例
2 学説
? 検討
<b>第4章 外国判決承認要件としての相互保証</b>
<b>――その現代的意義</b>
? はじめに
? 若干の比較法的考察
1 序論
2 ドイツ
3 オーストリア
4 その他の国における状況
5 比較法的概観のまとめ
? 日本における議論
1 判例
2 学説
? まとめと検討
1 日本法の特徴
2 相互保証の私益的構成
3 相互保証をめぐるその他の諸問題
4 結語
<b>第?部 効果論</b>
<b>第1章 外国判決の効力</b>
<b>――総論的考察</b>
? 問題の所在
? ドイツ法系における外国判決の効力論
A ドイツにおける議論
1 固有法
2 二国間条約
3 多国間条約(規則)
B オーストリアにおける議論
1 学説
2 判例
C スイスにおける議論
1 学説
2 連邦司法省の見解
3 連邦裁判所の見解
? 日本における外国判決の効力論
1 学説
2 判例
? 検討
1 諸説の検討
2 承認国法による判決効制限の可否
3 承認国法による判決効拡張の可否
4 関連問題
<b>第2章 訴え却下判決の国際的効力</b>
<b>――国際裁判管轄を否定した外国判決の効力をめぐって</b>
? はじめに
1 国際取引における法適用関係の不安定性
2 EU における試みと本章の検討課題
? 2012 年ヨーロッパ裁判所判決
1 事案
2 ヨーロッパ裁判所の判断
? ドイツにおける議論状況
1 承認対象
2 外国で下された訴え却下判決の国内的効力
3 ヨーロッパ裁判所2012年判決に対する反応
? 検討
1 ヨーロッパで活動する日本企業(日本人)への影響
2 日本法の解釈
? まとめと展望
<b>第2章補論 訴え却下判決の既判力をめぐる国内訴訟法の議論との関係</b>
<b>第3章 執行判決訴訟の法的性質について</b>
? はじめに
? 日本における議論
1 学説
2 判例
? ドイツにおける議論
1 学説
2 判例
? 検討
1 属地的性質の妥当性
2 確認訴訟説における判決国法と執行国法の関係
3 外国判決が判決国で効力を失った場合の扱い
4 給付訴訟説について
? 結語
<b>第?部 法律要件的効力</b>
<b>外国での訴え提起と消滅時効の中断</b>
? 問題の所在
? 若干の比較法的概観
1 時効の性質決定――その比較法的対立の素描
2 中断の要件――ドイツにおける議論
? 日本法の解釈
1 時効の性質決定
2 中断の要件
? まとめ
<b>第?部 まとめ</b>
初出一覧
事項索引
条文索引
判例索引
外国判決の承認
芳賀 雅顯[ハガ マサアキ]
著・文・その他
内容説明
現行民事訴訟法118条は、明治23年民事訴訟法に淵源を有するが、基本的には大きな変更を受けずに現在に至っている。この条文は外国判決の承認に関する多くの論点についてどのように対処してきたのか。市民生活が急速に国際化し、私法上の法的紛争もまた国際化が著しい現在、外国判決承認制度の目的とは何なのか、判決の国際的調和とは何か。外国判決承認制度を私権実現の制度であると明確に意識しながら、その要件及び効果の側面から、また比較法的手法も用いながら、繊細かつ明確に解き明かす。
目次
第1部 総論(序論;わが国における外国判決承認制度の歴史的概観)
第2部 要件論(間接的一般管轄;送達;公序;外国判決承認要件としての相互保証―その現代的意義)
第3部 効果論(外国判決の効力―総論的考察;訴え却下判決の国際的効力―国際裁判管轄を否定した外国判決の効力をめぐって;執行判決訴訟の法的性質について)
第4部 法律要件的効力(外国での訴え提起と消滅時効の中断)
第5部 まとめ
著者等紹介
芳賀雅顯[ハガマサアキ]
慶應義塾大学大学院法務研究科教授。1966年生まれ。明治大学法学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科博士前期課程修了、慶應義塾大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。ドイツ連邦共和国・レーゲンスブルク大学留学(ドイツ学術交流会、フンボルト財団)。明治大学法学部教授等を経て2013年より現職。専門は、民事訴訟法、とくに国際民事手続法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。