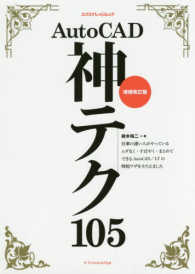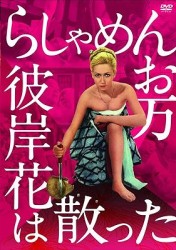出版社内容情報
本書は、30年にわたる会計制度改革と論争の流れとその主要論点を取り上げ、会計制度・会計学の意味と意義、今後の行方を論じる。会計が拘るべきもの、守るべき<ruby>構造<rt>しくみ</rt></ruby>は何か?
会計が果たすべきこと、担うべき<ruby>機能<rt>やくわり</rt></ruby>は何か?
会計の実践・研究は、企業活動を取り巻く経済社会の変動によって常に変化を迫られ、とくに1990年代のいわゆる「会計ビッグバン」以降、会計基準の国際的調和化(harmonization)、時価評価の導入、株主資本主義の拡大といった数々の激変にさらされてきた。
また、こうした変化は、激しい利害対立と学説上の論争を引き起こし、「何のための/誰のための会計か?」さらには「会計学は何の役に立つのか?」といった本質的問い掛けを呼び起こす。
本書は、こうした学問・実践の両面に対する問い掛けを受け、この30年ほどにわたる会計制度改革と論争の流れを鳥瞰し、その主要論点を取り上げながら、変容する会計制度・会計学の意味と意義、そして今後の行方を論じる。
緒 言
謝 辞
引用について
<b>序章 会計と会計学</b>
会計と会計学/『会計発達史』における会計学/近代会計学の父ルカ・
パチョーリ/会計に固有のもの,あるいは会計の特徴
<b>第1部 会計が拘るべきもの――守るべき<ruby>構造<rt>しくみ</rt></ruby>は何か</b>
<b>第1章 複式簿記への固執と未来指向の否定</b>
[単式簿記→複式簿記]の否定/複式簿記/複式簿記の前の簿記/会計
責任/スチュワードシップ
<b>第2章 公正価値会計という行き方</b>
現在価値は時価なのか/[原価vs.時価]と種々の会計システム/「測
定属性」/[原価vs.時価]と種々の会計システム(続)/取得原価会
計の短所と,しかし,それが支持されてきた事訳/現在価値の擡頭/
公正価値/公正価値ないし現在価値と情報の有用性
<b>第3章 取得原価会計の存在理由</b>
取得原価主義会計論/取得原価会計の論拠/アカウンタビリティ説/会
計企業経験記録説/貨幣(名目)資本による損益計算説/収支計算によ
る損益計算説/客観性としての原価説/取得原価会計の必然性ないし存
在理由/実現主義と名目資本維持/名目資本維持の性格と意義
<b>第4章 収益費用アプローチ,取得原価主義,そして名目資本維持</b>
会計をして会計たらしめているもの/収益費用アプローチ/取得原価主
義/名目資本維持
<b>第5章 発生主義の存在理由</b>
発生主義と現金主義/現金主義と清算/発生主義と現金主義(続)/実
現と対応/もたらしたもの,もたらされたもの
<b>第6章 減価償却思考確立の胚胎と逡巡</b>
固定資産の認識/減価償却の意義/「depreciation」/複会計システ
ム/取替法と廃棄法/漸うか
<b>第7章 会計の構造的枠組みの境界</b>
問題の所在/粗筋/純資産の部の導入/中間独立項目と資本直入項目/
曖昧さの排除/純利益と包括利益
<b>第2部 会計が果たすべきこと――担うべき<ruby>機能<rt>やくわり</rt></ruby>は何か</b>
<b>第8章 財務会計論の前提としての株式会社論</b>
株式会社の要件と起源/「株式会社」と「joint-stock company」/ロ
シア会社/ジョイント?ストック・カンパニーと株式会社/会計が行わ
れる状況
<b>第9章 債権者保護と株主の責任</b>
株主と経営者の関係/債権者保護と利害調整/有限責任制と債権者保
護/利害調整機能における計算/情報提供の意義/利害調整機能への集
約
<b>第10章 財務会計と管理会計</b>
山桝を取り上げることについて/「会計」の定義と会計学の対象/二つ
の会計における疑義/財務会計と管理会計/「財務」概念の拡大の可能
性
<b>第11章 簿記の機能と会計との関係</b>
山桝説/計算は簿記か/簿記と財務諸表の作成/「簿記」の定義の意
義/複式簿記と単式簿記
<b>第12章 近代会計成立史論の展開</b>
近代会計の成立プロセス/イギリスと鉄道/イギリス会計史論の先駆/
固定資産と複会計システムと減価償却/オランダ,そしてイギリス/
会計法制度(会社法会計制度)/会計プロフェッションと会計学
<b>第13章 会計士監査史論の展開</b>
通説/簿記監査/英米の異同/財務諸表の規則準拠性/専門的判断
<b>結 章 公正性と客観性</b>
会計の意義・目的と公正性/「公正性」概念論/「公正性」概念論の先
駆/[公正性vs.有用性]/公正性と客観性/取得原価と客観性/客観
性の相対性/エピローグ
文献リスト
索 引
著者紹介
友岡 賛[トモオカ ススム]
著・文・その他
内容説明
会計が拘るべきもの、守るべき構造は何か?会計が果たすべきこと、担うべき機能は何か?前々著『会計学の基本問題』(2016年)の続篇。
目次
会計と会計学
第1部 会計が拘るべきもの―守るべき構造は何か(複式簿記への固執と未来指向の否定;公正価値会計という行き方;取得原価会計の存在理由;収益費用アプローチ、取得原価主義、そして名目資本維持;発生主義の存在理由;減価償却思考確立の胚胎と逡巡;会計の構造的枠組みの境界)
第2部 会計が果たすべきこと―担うべき機能は何か(財務会計論の前提としての株式会社論;債権者保護と株主の責任;財務会計と管理会計;簿記の機能と会計との関係;近代会計成立史論の展開;会計士監査史論の展開)
公正性と客観性
著者等紹介
友岡賛[トモオカススム]
慶應義塾大学卒業。慶應義塾大学助手等を経て慶應義塾大学教授。博士(慶應義塾大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。