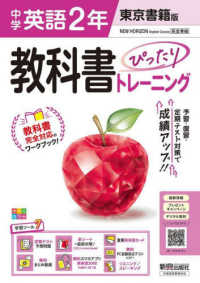内容説明
失踪とは何か。その不条理さ、不可解さ、やりきれなさは、何に由来するのか。現在でも日本国内で年間に数千件規模のペースで生じている隠れた社会問題、失踪―。失踪が惹起する実存的な問いを突きつめ、あなたや私がそこにいる、という一見自明の事態を根底から見つめなおす、気鋭の力作。
目次
1 いま、失踪を問う意味(なぜ私たちは「親密な関係」から離脱しないのか;失踪の実態はどこまで把握可能か)
2 失踪の言説史(失踪言説の歴史社会学―戦後から現在までの雑誌記事分析)
3 当事者の語る失踪(失踪者の家族社会学;失踪者の家族をいかにして支援すべきか―MPSの取り組みから ほか)
4 「親密な関係」に繋ぎとめるもの(親密なる者への責任;現代社会と責任の倫理)
行為としての“失踪”の可能性
著者等紹介
中森弘樹[ナカモリヒロキ]
1985年生まれ。2015年、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(人間・環境学)。現在、日本学術振興会特別研究員(PD)、京都大学・立命館大学・京都造形芸術大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
39
家出、蒸発、夜逃げ、行方不明‥‥失踪を示す言葉は古くからあり、時代によって世間の視線は変わって来た。例えば、「無縁」という言葉は古くはムラ社会からの自由という意味合いがあったが、近年は不安の印象の方が強い。要は、家族という紐帯をどう捉えるか、なのだろう。最近はネット社会になり、繋がりすぎすら指摘されている。失踪という概念そのものがなくなりつつあるのかもしれない。そんな社会もちょっと息苦しい気がする。時には親密な関係から逃げ出すことを許容すること、逃げることを認めることも大事だと感じる。2019/07/26
buuupuuu
17
現代では、親密な関係を結ぶことは、承認を与えると同時に、責任を生じさせるものでもあるという。それはケアを行う責任も含む。失踪は、そのような責任を放棄することとして捉えられるから忌避されるのだ。しかし、そのような責任論は、ときに自己責任論とともに、個人に過剰な責任を負わせてしまう場合がある。著者はそこからの解放の可能性を失踪に探っている。ところで、責任を分散させる方向へと考えていくことは、やはり難しいのだろうか。ケア関係と親密圏のカップリングや親密圏のあり方を考え直してみることは、なかなか大変そうだ。 2022/01/30
kuukazoo
13
現代では人は伝統や慣習の縛りから解放され自由に生きられるはずが実感としては家族その他の人間関係が負担だったりする。「失踪」とはそういった人間関係からの離脱。一方、生死/所在不明連絡不能な状態が残された側にもたらす不条理感、困惑、怒りなどの感情の根拠は「親密なる者への責任」という規範意識だという。親密な関係においては「応答」する責任があり、ケアが必要な存在(子どもや病人等)に対しては尚更だが、こうした責任の過負荷が自己責任同様個人を苦しめているのも事実。個の自由/責任に対する自分のbiasにも気づかされる。2025/02/15
かやは
10
「失踪」という生死不明の「一方的なコミュニケーションの断絶」状態がもたらす影響と効用について、かなり具体的かつ詳細に分析している。昔の人は物事が起きる理由付けを神や妖怪に求め、意味があることとして解釈しようとした。意味の無いことがわかったしまった現代の生きづらさを感じる。ただ一つの場所に留まって辛い思いをし続けるより、一度その場から離れて失踪してしまったほうがその人自身のためになることもあるだろう。失踪することを許せる社会は救いのある社会なのかもしれない。 2018/12/07
kenitirokikuti
9
失踪を題材とした小説の書き手、代表は安部公房。失踪者が主人公な『砂の器』、失踪者を追うのが『燃えつきた地図』/映画『岸辺の旅』(黒沢清監督)は失踪者が幽霊として戻る話▲われわれの社会は進歩して自由になったが、実感として「人間関係」から自由になったのか。介護ひとつ取っても「重い」/失踪・家出・蒸発は1960〜70年に社会病理学の研究対象となったが、平成に途絶えた。ホームレスや「無縁」、夜逃げ、行方不明等に名前が変わったという解もある。2018/04/15