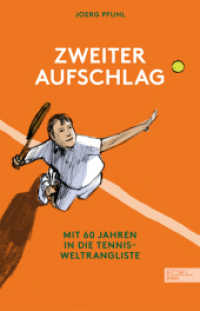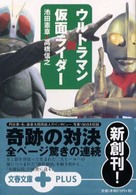内容説明
「語りえぬもの」、その先へ。『論考』で沈黙した哲学者は、「教育」を手がかりに再び語り出す。新進気鋭の若手が描く、「第三のウィトゲンシュタイン」
目次
プロローグ
第1章 ウィトゲンシュタインと教育学
第2章 教育の言語ゲーム
第3章 イニシエーションと訓練
第4章 言語・事物・規範性
第5章 子どもの他者性
第6章 語りえぬものの伝達
第7章 教育と言語の限界
エピローグ
著者等紹介
渡邊福太郎[ワタナベフクタロウ]
1981年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。博士(教育学)。現在、慶應義塾大学文学部助教。専門は教育哲学・教育思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
センケイ (線形)
4
少々難読だが、分類問題において記号接地すべきか、極限環境でのそうした問題を広い概念世界に応用できるのか、といった諸イメージが大変示唆に富む。加えて学習を開始できる条件についても賛否様々な見解が紹介されるため、やはり機械学習の汎用モデルを志すのであれば是非とも目を通したい一冊と言える。言語で取り扱いできる限界とその更新可能性についても議論があり、科学哲学とも通じる箇所にまた別の面白さがある。まだ理解の漠然としているところは、他の本も合わせつつ理解を膨らませていきたい。2019/06/27
Go_with_twill
3
言語ゲームや、他者性など、私自身が今まで知らなかった哲学者ウィトゲンシュタインの教育への情熱を知ることができて興味深かった。 中でも、どれだけ突き詰めようとも言語化できないものはあって、それが分かっていながらも無駄になってしまう努力を続ける人間、というところに共感しました。伝えるという作業を日々している以上、この部分を忘れずまた少しでも克服できるようにしないとなぁと思いましたね。2017/09/18
すんだ
0
※初め1/5程度のみ <一言><メモ>Witgensteinの言語論的転回に影響されて、「価値中立的な方法」である分析的教育学が登場/建築家の言語ゲームこそ原初の言語ゲームである:言葉と指示対象の一対一対応をベースとしたコミュニケーション/但し原初の言語ゲームは、言語ゲームの原初のあり方として想定されるのみであり、現実には、言葉を覚え始める子供においてすら起こらない(後代学者の解釈) ※記述内容を厳密に振り返らずに書いているため言葉の用法等にずれのある可能性あり2017/08/20
-

- 電子書籍
- エレガンスイブ 2025年10月号
-
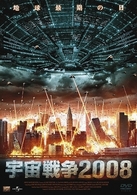
- DVD
- 宇宙戦争2008