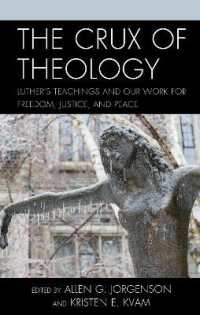内容説明
クルアーン論の世界的名著、待望の邦訳。
目次
第1章 意味論とクルアーン
第2章 歴史のなかに配置されたクルアーンのキー・ターム
第3章 クルアーンの世界観の基本構造
第4章 アッラー
第5章 神と人間の存在論的連関
第6章 神と人間のコミュニケーション的連関(1)―非言語的コミュニケーション
第7章 神と人間のコミュニケーション的連関(2)―言語的コミュニケーション
第8章 ジャーヒリーヤとイスラーム
第9章 神と人間の倫理的連関
著者等紹介
井筒俊彦[イズツトシヒコ]
1914年、東京都生まれ。1949年、慶應義塾大学文学部で講義「言語学概論」を開始、他にもギリシャ語、ギリシャ哲学、ロシア文学などの授業を担当し、英文処女著作Language and Magicなどを発表。1959年から海外に拠点を移しマギル大学やイラン王立哲学アカデミーで研究に従事、エラノス会議などで精力的に講演活動も行った。この時期は英文で研究書の執筆に専念した。1979年、日本に帰国してからは日本語による著作や論文の執筆に勤しみ『イスラーム文化』『意識と本質』などの代表作を発表した。93年、死去
鎌田繁[カマダシゲル]
東京大学名誉教授、日本オリエント学会前会長。イスラーム神秘思想・シーア派研究
仁子寿晴[ニゴトシハル]
同志社大学非常勤講師。イスラーム哲学・中国イスラーム思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
7
クルアーン自身に語らせる場合、ムハマンドが生きた時代の語(アッラー、イスラーム、ムスリム等)の語用の相関を調べ、当時の状況と意味を想定する手順を要する。著者は通時的意味論を用いてクルアーン後の語用を排してクルアーン前のベドウィン時代の語用と対照し、共時的意味論によってクルアーンにおいて旧来の語用が二項対立的に編成し直される様を構造化する。本書後半は特に「神と人間」の二項をに注目し、無知の反対語ヒルムが後退する一方、啓示と祈りの絶対的区別が強調され、神の慈悲と怒りが人の信仰の有無の二項に関わる点が示される。2021/01/31
bapaksejahtera
6
イスラム基幹概念について開教前後の意味的変容を包括的に論ずる。内容は個別アラビア語変化を追うだけでなく諸観念に纏わる意味的変容を通じた世界観の動的解明である。本書は英文著作の翻訳だが、同内容は「イスラーム生誕」で文庫出版されている。さて本書の主論ではないが、神が天使ジブリールを通じアラビヤ語を以てムハンマドに下したクルアーンは、神の「ラング」であり、アラビア語はその際パロールの用に適った訳で、決して神聖言語ではない、と井筒は記す。非アラブのイランにおいて、非アラブのイスラム理解に通じた著者らしい記述である2020/10/17
人生ゴルディアス
4
イスラムについて全く知らないので読んでみた。著者がコーランの日本語注釈(如何なる者もコーランの翻訳はできない)を書いたのを知ってたので、手に取ってみる。どうやら本書では、コーランに出てくる言葉のうち、ジャーヒリーヤ期とそれ以降での言葉の変化のようなものを記そうとしているのだが、これはどう見ても語用論であって、意味論ではない。冒頭のほうでは言語哲学的な意味論を匂わせる説明があったので、言語がいかようにして「意味」を持ちうるのかの意味で「アッラー」とかを扱うかと思ったのだけど、そうではなかった。2017/08/24