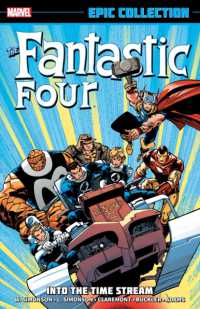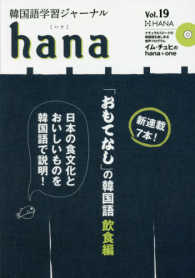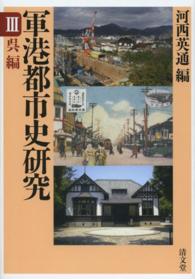出版社内容情報
「自然地理学」入門書の決定版、第5版。環境変化、現象とその原因追究、環境変化予測のための最新データが満載。データを更新した。▼地球でいま何が起きているのか?
温暖化をはじめとする地球環境問題および地震・火山災害などの諸課題を自然地理学の立場から解説した入門書。大気・海洋・地盤環境の過去から現在までの変化過程とその原因、さらに将来予測について、豊富な図表・写真を交えて平易に説明した待望の増補改訂版。
地球全体や身近な地域の自然環境および災害について考えるとき,過去から現在まで大気・海洋・地盤などの環境はどのように変化してきたのか,現在どんな現象が進行しているのか,それらの原因やメカニズムはどの程度明らかになっているのか,今後どのような変化が予測されるかをそれぞれ正確に理解し,客観的な目をもつことはとても大切なことです。
本書は,自然地理学の立場から,こうした視点をもつために必要な項目をまとめたものです。扱う内容が多岐にわたるためページ数の制約はありますが,それぞれの項目について考察の基礎になる図表をできるだけ多く載せたうえで解説を加えました。さらに詳しい内容について知りたい方のために,引用図書のほかに参考図書のリストも加えました。
地理学的なものの見方・考え方の特徴は,空間的・時間的な解析を行って,それぞれにズーム機能をもたせて考察する点にあります。すなわち,空間的には,地球規模で起きていることから身近な地域にまで目を向け,それらの結びつきを考えます。また時間的には,最近数十年間あるいは数百年間に起こってきた現象が,より長期的な時間スケールの変化の中ではどのように位置づけられるかに注目します。こうした柔軟な姿勢をもつことで,さまざまな現象や問題をより総合的にとらえることができるようになります。
はじめに
本書の構成
<b>1章 地球環境変遷とその原因</b>
<b>1.1 地球環境の歴史と現在の位置づけ</b>
<b>1.2 第四紀における気候変化と海面変化</b>
1.2.1 氷期・間氷期サイクル
1.2.2 気候変化と海面変化の関係
<b>1.3 気候変化の原因</b>
1.3.1 気候変化に関わる諸要因
1.3.2 惑星地球の周期的運動 ――ミランコビッチ・サイクル
1.3.3 海洋の深層循環 ――海のコンベアーベルト
1.3.4 太陽活動 ――太陽黒点数の周期的変化
1.3.5 火山活動による日傘効果
<b>2章 古気候・古環境の復元</b>
<b>2.1 現在の気候の特徴および古気候の復元方法</b>
2.1.1 現在の気候分布
2.1.2 地形が気候に及ぼす影響
2.1.3 古気候・古環境の復元方法
<b>2.2 氷河の痕跡を用いた古気候復元</b>
2.2.1 現在の氷河分布と氷河の流動
2.2.2 氷河が残す痕跡
2.2.3 過去の氷河分布に基づく氷期の復元
<b>2.3 化石による古気候・古環境復元</b>
2.3.1 化石の種類と復元できる環境要素
2.3.2 花粉化石による古植生・古気候復元
2.3.3 動物化石による古環境復元
<b>2.4 酸素同位体を用いた古気候・古環境復元</b>
<b>3章 旧海水準および海岸線の復元</b>
<b>3.1 海面変化の原因および旧海水準の復元方法</b>
3.1.1 海面変化の原因
3.1.2 地形による旧海水準の復元
3.1.3 堆積物による旧海水準の復元
<b>3.2 相対的海面変化曲線</b>
3.2.1 相対的海面変化曲線の地域差
3.2.2 アイソスタシー
<b>3.3 沿岸地域における古地理変遷</b>
3.3.1 海面変化に伴う海岸線の移動
3.3.2. 古地理の復元
<b>4章 年代測定の方法</b>
<b>4.1 放射性同位体を用いた年代測定法</b>
4.1.1 放射性同位体による年代測定の原理
4.1.2 放射性炭素同位体(14C)による年代測定法
<b>4.2 その他の年代推定法</b>
4.2.1 火山降下物(テフラ)による年代推定法
4.2.2 年輪年代法
<b>5章 地球環境の諸問題(1)</b>
<b>5.1 地球温暖化</b>
5.1.1 気温および二酸化炭素濃度変化の実態と温暖化のメカニズム
5.1.2 21世紀の気温変化予測および温暖化の地球環境への影響
5.1.3 地球温暖化対策と問題点
<b>5.2 ヒートアイランド現象</b>
5.2.1 ヒートアイランド現象の実態と原因
5.2.2 ヒートアイランド対策と問題点
<b>5.3 オゾン層破壊</b>
5.3.1 地球大気の構造とオゾン層
5.3.2 オゾン層破壊の実態
5.3.3 オゾン層破壊の原因 ――フロンによるオゾン層破壊の過程
5.3.4 オゾン層破壊の防止策と問題点
<b>5.4 エルニーニョ現象/ラニーニャ現象</b>
5.4.1 エルニーニョとエルニーニョ現象
5.4.2 エルニーニョ現象/ラニーニャ現象の原因と経過
5.4.3 エルニーニョ現象/ラニーニャ現象と異常気象
<b>6章 地球環境の諸問題(2)</b>
<b>6.1 地球砂漠化</b>
6.1.1 砂漠化の定義と分布
6.1.2 砂漠化の原因と過程
6.1.3 砂漠化対策と問題点
<b>6.2 地球の水資源</b>
6.2.1 水需要の実態と21世紀の水資源
6.2.2 乾燥地域の水資源 ――イスラエルを例にして
<b>6.3 エネルギー資源</b>
6.3.1 エネルギー資源の現状
6.3.2 新たなエネルギー資源
<b>7章 地震活動</b>
<b>7.1 地震の基礎</b>
7.1.1 地震の種類 ――日本周辺で発生する地震を中心に
7.1.2 震源と震源域
7.1.3 マグニチュードと震度
<b>7.2 地球上の地震分布と過去の主要地震</b>
7.2.1 世界の地震分布と主要地震
7.2.2 日本列島およびその周辺海域の地震分布と主要地震
<b>8章 プレート境界で発生する地震(プレート境界型地震)</b>
<b>8.1 プレートテクトニクス</b>
8.1.1 プレートテクトニクス誕生までの経緯
8.1.2 地球上のプレートおよびプレート境界の分布
8.1.3 プルームテクトニクス
<b>8.2 日本列島周辺のプレート分布とプレート境界型地震</b>
8.2.1 プレートテクトニクスから見た日本列島
8.2.2 沈み込み境界で発生する地震のメカニズム
8.2.3 南海トラフ・駿河トラフで発生する地震
8.2.4 相模トラフで発生する地震
8.2.5 日本海溝で発生する地震 ――東北地方太平洋沖地震の位置づ
け
<b>9章 活断層の活動によって発生する地震(活断層型地震)</b>
<b>9.1 活断層の認定方法</b>
9.1.1 活断層の定義および分類
9.1.2 活断層の調査方法
<b>9.2 日本における活断層分布と活断層型地震</b>
9.2.1 日本の活断層分布
9.2.2 濃尾地震 ――根尾谷断層
9.2.3 兵庫県南部地震 ――野島断層
<b>10章 地震災害の実態と将来予測</b>
<b>10.1 津波</b>
10.1.1 津波の特性
10.1.2 遠地津波
10.1.3 津波地震
<b>10.2 地盤の液状化現象</b>
10.2.1 液状化の発生メカニズム
10.2.2 液状化被害の特徴
10.2.3 液状化が起こりやすい地形条件
<b>10.3 地震の将来予測と地震防災</b>
10.3.1 地震の将来予測
10.3.2 地震および地震災害の多様性 ――関東大震災、阪神・淡路
大震災、東日本大震災から学ぶこと
10.3.3 地震ハザードマップ
<b>11章 火山活動と火山災害</b>
<b>11.1 地球上の火山分布と噴火様式</b>
11.1.1 火山の分布
11.1.2 マグマの種類と火山の噴火様式
<b>11.2 火山噴火と災害</b>
11.2.1 世界の火山災害
11.2.2 日本における火山噴火と災害
11.2.3 火山ハザードマップ
<b>12章 水害・土砂災害</b>
<b>12.1 水害・土砂災害の地域性と原因</b>
12.1.1 世界および日本における水害・土砂災害
12.1.2 水害・土砂災害の原因
12.1.3 日本の河川の特徴
<b>12.2 水害・土砂災害の実態</b>
12.2.1 日本の水害・土砂災害
12.2.2 中国の水害
12.2.3 ネパールの水害・土砂災害
<b>12.3 水害対策の歴史</b>
12.3.1 治水の方法
12.3.2 利根川流域の水害と東遷工事
12.3.3 信濃川下流域の水害と放水路建設
12.3.4 武田信玄による甲府盆地の治水
12.3.5 水害ハザードマップ
<b>13章 人為的要因による災害</b>
<b>13.1 地盤の沈下現象</b>
13.1.1 地下水採取による地盤沈下
13.1.2 構造物や埋立て土砂の荷重による地盤沈下
<b>13.2 海岸侵食</b>
13.2.1 海岸侵食の原因と過程
13.2.2 海岸侵食の実態
13.2.3 海岸侵食対策
<b>14章 身近な地形と人間活動</b>
<b>14.1 地形情報の解析方法</b>
14.1.1 地図および空中写真の利用
14.1.2 GIS(地理情報システム、地理情報科学)
<b>14.2 平野の地形</b>
14.2.1 平野を構成する地形要素
14.2.2 関東平野の地形
14.2.3 東京都の地形 ――千代田区・中央区・港区周辺を例にして
14.2.4 横浜周辺の地形
<b>14.3 砂州地形の発達史と人間活動</b>
14.3.1 砂州地形発達史の復元
14.3.2 砂州地形発達史における共通性と地域性
14.3.3 人間活動の場としての砂州地形
引用図書
参考図書
索引
松原 彰子[マツバラ アキコ]
松原 彰子
東京都生まれ
1987年 東京大学大学院理学系研究科地理学博士課程修了
現在 慶應義塾大学経済学部教授、理学博士
専門 自然地理学、第四紀学
著書・翻訳
『人文地理学―その主題と課題―』(共著、2005年、慶應義塾大学出版会)、『日本の地形5 中部』(分担執筆、2006年、東京大学出版会)、『ジオ・メディアの系譜―進化する地表象の世界―』(共著、2010年、慶應義塾大学出版会)、『日本の海岸』(分担執筆、2013年、朝倉書店)、"Holocene Geomorphic Development of Coastal Ridges in Japan."(2015年、Keio University Press)、『図説 世界の地理 第8巻 フランス』(共訳、1999年、朝倉書店)、『オックスフォード地理学辞典』(共訳、2003年、朝倉書店)
内容説明
地球でいま何が起きているのか。温暖化をはじめとする地球環境問題および地震・火山災害などの諸課題を自然地理学の立場から解説した入門書。大気・海洋・地盤環境の過去から現在までの変化過程とその原因、さらに将来予測について、豊富な図表・写真を交えて平易に説明した待望の増補改訂版。
目次
地球環境変遷とその原因
古気候・古環境の復元
旧海水準および海岸線の復元
年代測定の方法
地球環境の諸問題
地震活動
プレート境界で発生する地震(プレート境界型地震)
活断層の活動によって発生する地震(活断層型地震)
地震災害の実態と将来予測
火山活動と火山災害
水害・土砂災害
人為的要因による災害
身近な地形と人間活動
著者等紹介
松原彰子[マツバラアキコ]
東京都生まれ。1987年東京大学大学院理学系研究科地理学博士課程修了。現在、慶應義塾大学経済学部教授、理学博士。専門は自然地理学、第四紀学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。