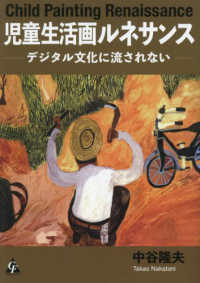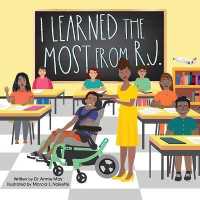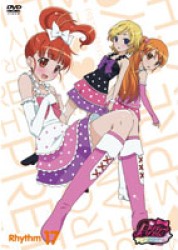出版社内容情報
クジラは進化生物学の研究対象として魅力的である。短時間で姿を変えた生物はいない。変化の裏側でどのようにゲノムが進化したのか。
▼「クジラの研究者になるのもいいな」
小笠原から極北アラスカ、そして南太平洋バヌアツへ。嗅覚をキーワードに、クジラの進化を追いかけた。日本の調査捕鯨問題にも一石を投じた一冊。
クジラは進化生物学の研究対象として魅力的である。始新世のわずか1000万年程度の短時間で、これほどまで劇的に姿を変えた生物はめったにいない。極端な例の中にこそ、普遍的な法則があぶり出される。形態の劇的な変化の裏側で、どのようにゲノムが進化したのか。生物の進化を考えるにあたって、クジラはこれからも重要な手がかりを与えつづけてくれるにちがいない。<「あとがき」より>
第1章 海に生きる羊膜類
1.1 海から陸へ、そして陸から再び海へ
1.2 海に棲むウシ ―― 鯨類の進化
1.3 クジラの視物質
コラム1 単系統・側系統・多系統
第2章 嗅覚受容体遺伝子
2.1 化学物質をニオイとして嗅ぎ分ける
2.2 脊椎動物の陸上環境進出と嗅覚受容体レパートリーの変化
2.3 鯨類の嗅覚受容体遺伝子
第3章 ホッキョククジラ
3.1 四肢動物海洋環境適応会議
3.2 「嗅覚」とは何か
3.3 ホッキョククジラの嗅覚器官
3.4 クジラの鼻はいくつある?
コラム2 コマッコウの左右の鼻道
第4章 塩基置換と進化
4.1 天は二物を与えず?
4.2 反響定位と嗅覚
4.3 同義置換・非同義置換
コラム3 鯨類の聴覚の進化
第5章 ウミヘビ
5.1 ウミヘビに魅せられて
5.2 収斂進化
5.3 バヌアツ
5.4 バヌアツアオマダラの嗅覚受容体遺伝子
コラム4 カヴァ
第6章 ゲノム
6.1 ヒゲクジラのゲノムを解読する
6.2 ド=ブラン・グラフ
6.3 ゲノムアセンブル
第7章 嗅 球
7.1 クジラの嗅球と変異ネズミ
7.2 受容体から嗅球へ:1糸球-1受容体ルール
7.3 クジラの嗅球の背側領域
7.4 化 石
第8章 クジラ研究と調査捕鯨
8.1 ミンククジラゲノム
8.2 先住民捕鯨を守るため
8.3 英国王立協会紀要
8.4 南氷洋捕鯨に思う
おわりに
参考文献
索 引
【著者紹介】
斎藤 成也
1957年生まれ。テキサス大学ヒューストン校生物学医学大学院修了(Ph.D.)。現在は国立遺伝学研究所教授。おもな著書に『DNAから見た日本人』(ちくま新書)、『ゲノム進化学入門』(共立出版)、『Introduction to Evolutionary Genomics』(Springer)、『日本列島人の歴史』(岩波ジュニア新書)などがある。
内容説明
小笠原から極北アラスカ、そして南太平洋バヌアツへ。嗅覚をキーワードに、クジラの進化を追いかけた。日本の調査捕鯨問題にも一石を投じた一冊。
目次
第1章 海に生きる羊膜類
第2章 嗅覚受容体遺伝子
第3章 ホッキョククジラ
第4章 塩基置換と進化
第5章 ウミヘビ
第6章 ゲノム
第7章 嗅球
第8章 クジラ研究と調査捕鯨
著者等紹介
岸田拓士[キシダタクシ]
1976年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。博士(理学)。現在は京都大学野生動物研究センター特定助教
斎藤成也[サイトウナルヤ]
1957年生まれ。テキサス大学ヒューストン校生物学医学大学院修了(Ph.D.)。現在は国立遺伝学研究所教授
塚谷裕一[ツカヤヒロカズ]
東京大学大学院理学系研究科教授
高橋淑子[タカハシヨシコ]
京都大学大学院理学研究科生物科学専攻教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yooou
Tsukasa Fukunaga
Masaki
ヤナセトモロヲ
YK