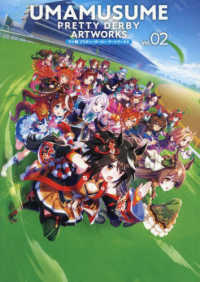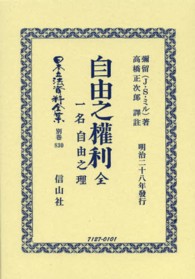出版社内容情報
本書では、上巻と結実した「家計労働供給」、「賃金較差」、「家計の就業パターン」、3つの小尾理論の初期から中期の論文を収録。
計量経済学研究の第一人者の研究を集成。
日本の計量経済学研究に大きな功績を遺した小尾惠一郎教授の論文を集成する著作集、ついに完結。
本書では、上巻『家計労働供給の観測と理論』として結実した「家計労働供給の確率的理論」、「賃金較差の理論」、「家計の就業パターンの発生理論」という3つの小尾理論が形成される過程の初期から中期にかけての論文を収録。
1950年代から1960年代の様々な機会に発表された選りすぐりの論文によって、この3つの理論に結実していく過程をあとづける構成となっており、小尾理論の生まれる経緯をつぶさに辿ることができる。
編者はしがき――解題に代えて
凡 例
?T 賃金指数の意味と算定
?U 蓄積、生産要素相対価格および利用度の構造的関係
――生産函数の測定と分配率の再考を含めて
?V 実物給与の機能について――規模別産業別分析の一階梯
?W 生産構造の計測と与件――生産函数計測における工学的資料の援用に
ついて
?X 賃金・雇用分析の計量的基礎――家計の労働供給機構の計測と理論
?Y 余暇・所得選好場と変位の計測
?Z 賃金と労働時間の較差――較差の構造と推移のメカニズム
?[ 応募方程式による労働市場の分析――戦前紡績業における地域間労働
移動
?\ 経済発展と就業機構――労働供給機構に関する経験的接近
?] 労働供給理論における恒常所得仮説の経験的有効性に関する問題点
? 労働供給の理論――その課題および帰結の含意
初出一覧
主要著作一覧
索 引
【著者紹介】
小尾 惠一郎
慶應義塾大学名誉教授、経済学博士(慶應義塾大学、1966年)
1950年慶應義塾大学(旧制)経済学部卒業、同経済学部副手、53年同助手、57年同助教授、67年同教授、93年名誉教授。この間、1963-64年ハーバード大学留学、81-87年慶應義塾大学産業研究所副所長、1987-91年同所長。
主な著作に、「労働の供給」(寺尾琢磨編『日本経済の分析 4 雇用』春秋社、1959年)、「賃金と労働時間の較差――較差の構造と推移のメカニズム」(中山伊知郎編『賃金問題と賃金政策』東洋経済新報社、1959年)、「主体均衡の理論」(熊谷尚夫・大石泰彦編『近代経済学 (1)』有斐閣、1960年)、「仮説とその検証――仮説の有効性について――」(慶應義塾経済学会編『経済学方法論の諸問題』東洋経済新報社、1967年)、「臨界核所得分布による勤労家計の労働供給の分析」(『三田学会雑誌』第62巻1号、1969年)、「労働市場の理論」(西川俊作編『労働市場』日本評論社、1971年)、『計量経済学入門――実証分析の基礎――』(現代経済学入門(10)…
内容説明
小尾が1950年代から1980年代に著した論文・小論を中心に蒐集・編纂したものであり、上下2巻から構成される。ここに収録したいずれの論考も、KEOの経済学の伝統―理論と観測との双方に確率論的基礎を備えせしめること、多様な現象を同一少数個の原理によって叙述する一般理論の構築を目指すこと、一般均衡体系において理論と観測を位置づけること、を明確に体現しており、今日のKEOの研究姿勢を基礎づけるものと言える。
目次
1 賃銀指数の意味と算定
2 蓄積、生産要素相対価格および利用度の構造的関係―生産函数の測定と分配率の再考を含めて
3 実物給与の機能について―規模別産業別分析の一階梯
4 生産構造の計測と与件―生産函数計測における工学的資料の援用について
5 賃金・雇用分析の計量的基礎―家計の労働供給機構の計測と理論
6 余暇・所得選好場と変位の計測
7 賃金と労働時間の較差―較差の構造と推移のメカニズム
8 応募方程式による労働市場の分析―戦前紡績業における地域間労働移動
9 経済発展と就業機構―労働供給機構に関する経験的接近
10 労働供給理論における恒常所得仮説の経験的有効性に関する問題点
11 労働供給の理論―その課題および帰結の含意
著者等紹介
小尾惠一郎[オビケイイチロウ]
1927‐1997年。慶應義塾大学名誉教授、経済学博士。1950年慶應義塾大学(旧制)経済学部卒業、同経済学部副手、53年同助手、57年同助教授、67年同教授、93年名誉教授。この間、1963‐64年ハーバード大学留学、81‐87年慶應義塾大学産業研究所副所長、87‐91年同所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 木材の加工 木材の利用