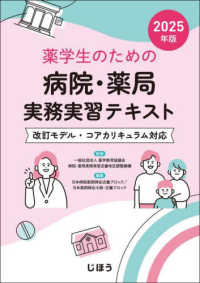内容説明
10代の子どもの「うつ病」や「うつ気分」について症状、医師へのかかり方、治療、学校生活の送り方などをはじめ、家庭でどう協力していくのが望ましいか、分かりやすく説明します。
目次
第1章 「うつ病」の理解:「うつ気分」と「うつ病」(「うつ病」は稀なものではありません;思春期の子どもの「うつ気分」 ほか)
第2章 「うつ病」にともなう様々な状態―発達障害との関連も含めて(反抗的な行動について;「うつ」と反抗・衝動との関係 ほか)
第3章 「うつ気分」を引き起こす出来事にどう対応するか(うつ病の予防への試み;子どものうつ病へのリスクを知るために ほか)
第4章 うつ病の治療について知ってほしいこと(どんなときに病院やクリニックを訪れるとよいのでしょうか;医療機関を訪ねたなら ほか)
著者等紹介
猪子香代[イノコカヨ]
猪子メンタルクリニック院長。東京女子医科大学非常勤講師。専門は児童精神医学。日本小児精神神経学会認定医。1982年東京女子医科大学卒業。東京女子医科大学病院小児科、名古屋大学病院精神科、愛知県一宮市民病院今伊勢分院精神科、愛知県精神保健センター、愛知県厚生連更生病院精神科を経て、1997年名古屋大学病院精神科講師、1998年名古屋大学大学院児童精神医学助教授、2001~2011年東京都精神医学総合研究所副参事研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
2
初めのほうに書かれていたとおり、「子どもの」というタイトルではあるが、若者に至るまで、いや、その先の年齢も含めてあてはめて考えていい本だと思う。特に、子どもの間はまさに成長し変化していく時期でもあるし、子どもによって成長の度合い(スピード)も違うので、ついつい見逃したり勘違いしてしまうことが多いのだと思う。それだけでなく、うつと発達障害とかいろいろなところとの関係性もある。とにかく、慌てないでゆっくりとということだけは、再認識できた。職場でも、対応しているので、改めていろいろ考える点が多い。2012/11/24
りら
0
図書館で借りて読んだ。今の時代を生きるこどもたちの息苦しさが伝わってくるようだった。うつ病であるなしに関わらず、そうしたこどもたちに家族や周囲の人間がどう接していくかという点で、大変参考になった。知っているのと知らないのとでは、対応の仕方が違うと思う。大学の出版物だが、読みやすかった。2013/03/29
-

- 洋書
- MANTRA BOX