出版社内容情報
1870年代から1913年にかけての国際銀行業のアジアにおける活動を、金融機関の内部資料などを駆使して分析した金融史研究。
▼本邦初の本格的国際金融史研究
運輸・通信技術革命による第1次グローバリゼーションは、国際貿易の量と質、速度を劇的に変えた。そして、列強諸国から世界へ進出した銀行家たちは、単なる資本輸出にとどまらず、貿易金・融に決定的な役割を果たしたのだった。
各国に眠る金融機関の1次資料などを発掘し、1870年代から1913年にかけての国際銀行のアジアにおける活動を精緻に分析。さらにロンドン金融市場がアジア経済発展に果たした役割を解明する本格的金融史研究。
序文
凡例
<b><u>第1編 グローバリゼーションと国際銀行</u></b>
<b>第1章 第一次グローバリゼーションとアジアにおける英系国際銀行</b> 西村 閑也
1 序
2 運輸通信革命
3 グローバリゼ―ションと貿易金融
4 アジア現地における英系国際銀行
5 アジアにおける英系国際銀行と非英系国際銀行
6 結語
<b>第2章 国際資本移動と国際労働移動</b>
<b>1870-1913年</b> 菅原 歩
1 序
2 国際資本移動 1870-1913年
3 国際労働移動 1870-1913年
4 結語
<b>第3章 海底電信ケーブルの敷設と国際銀行</b> 鈴木 俊夫
1 序
2 海底電信ケーブルの敷設
3 通信時間の短縮
4 電信のビジネス利用と料金
5 電信と商取引構造の変化
6 国際銀行業と電信
7 結語
<b>第4章 国際銀行とロンドン金融市場</b> 鈴木 俊夫
1 序
2 英系海外銀行の英国における営業活動
3 英系海外銀行とロンドン割引市場
4 手形取引の例示
5 非英系国際銀行のロンドン支店の営業活動
6 結語
<b>第5章 銀本位制から金本位制へ</b>――アジア諸国 西村 雄志
1 序
2 インド
3 海峡植民地
4 蘭領東インド
5 シャムの通貨制度概観
6 仏領インドシナの通貨制度概観
7 結語
<b><u>第2編 英系国際銀行</u></b>
<b>第6章 国際銀行の前史</b> 菅原 歩
1 序
2 国際銀行設立の背景
3 王室特許状、株式銀行、株主有限責任
4 王室特許状と国際銀行の規制体系
5 各行の王室特許状?@
――オーストラレイジア銀行の事例
6 各行の王室特許状?A
――サウス・オーストラリア銀行の事例
7 各行の王室特許状の比較――業務の地理的範囲
8 王室特許状における銀行券の扱い
9 結語
<b>第7章 東洋銀行 1842-1884年</b> 鈴木 俊夫
1 序
2 19世紀前半期のアジア向け海外銀行設立ブーム
3 オリエンタル銀行の創業
4 1850年代の東洋銀行の経営
5 1860年代の東洋銀行の経営
6 1870年代の東洋銀行の経営
7 1880年代の東洋銀行の経営
8 結語――東洋銀行崩壊の要因
<b>第8章 香港上海銀行 1865-1913年</b> 西村 閑也
1 序
2 支店の業務
3 マーチャント・バンクとしての香港上海銀行
4 結語
<b>第8章補論 香港上海銀行ロンドン店 1875-1889年</b>
――David McLean Papersの検討を通じて 蕭 文嫻
1 為替業務
2 コルレス銀行との関係およびロンドン諮問委員会の設置
3 預金業務
4 アジアに進出した国際銀行間の協調行動
5 結語
<b>第9章 香港上海銀行ハンブルク支店 </b>
<b>1890-1913年</b> 蕭 文嫻
1 序
2 ドイツとアジアとの経済関係
3 アジアにおける国際銀行の業務展開
4 英系国際銀行ハンブルク支店の業務
5 結語
<b>第10章 チャータード銀行 1858-1890年</b> 北林 雅志
1 序
2 チャータード銀行のアジア支店の活動
3 1880年代のチャータード銀行
4 チャータード銀行の計算書類について
5 結語に代えて
<b>第11章 チャータード銀行 1890-1913年</b> 西村 閑也
1 序
2 チャータード銀行の成長 1890-1913年
3 業務の実態
付1 チャータード銀行本店のB/S 1899年6月30日
付2 チャータード銀行の現地貸付
付3 天津支店
<b>第12章 チャータード・マーカンタイル銀行</b>
<b>1853-1892年</b> 北林 雅志
1 序
2 チャータード・マーカンタイル銀行の設立と初期の活動
3 チャータード・マーカンタイル銀行の計算書類
4 1860年代初頭のチャータード・マーカンタイル銀行
5 ボンベイ・バブルとチャータード・マーカンタイル銀行
6 銀価の下落とチャータード・マーカンタイル銀行
7 チャータード・マーカンタイル銀行の解散と新銀行の設立
<b>第13章 マーカンタイル銀行 1892-1913年</b> 西村 閑也
1 マーカンタイル・バンク・オブ・インディアの成立
2 マーカンタイル銀行の成長
3 マーカンタイル銀行ロンドン本店
4 海外支店
5 結語
<b>第14章 英系国際銀行のパフォーマンス</b>
――総資産利益率と株価収益率を中心に 北林 雅志
1 序
2 英系国際銀行の動向
3 英系国際銀行の地域間比較
4 英系国際銀行のパフォーマンス
5 結語
<b><u>第3編 非英系国際銀行</u></b>
<b>第15章 ドイツ銀行・独亜銀行 1870-1913年</b> 赤川 元章
1 序
2 19世紀末のドイツ銀行業と東アジア
3 独亜銀行の発展と営業活動
4 独亜銀行の財務諸表の構成と本支店間の取引関係
5 独亜銀行の本支店活動と営業領域の特殊性
6 中国鉄道投資と独亜銀行
7 結語
<b>第16章 露清銀行・インドシナ銀行</b>
<b>1896-1913年</b> 矢後 和彦
1 序
2 パリ割引銀行(パリ国民割引銀行)
3 露清銀行
4 インドシナ銀行――支店業務を中心に
5 結語にかえて
<b>第17章 横浜正金銀行 1880-1913年</b> 西村 雄志
1 序――研究史概観
2 貿易金融の展開
3 阪神地方における横浜正金銀行の展開
4 結語にかえて――横浜正金銀行神戸支店の位置づけ
あとがき
参考文献
図表一覧
人名索引
企業名等索引
地理名等索引
語句索引
執筆者紹介
【著者紹介】
西村 閑也
法政大学名誉教授。
1953年東京大学経済学部卒業、同大学大学院社会科学研究科修士課程修了、1969年ロンドン大学(London School of Economics and Political Science)大学院経済学研究科博士課程修了、Ph.D. (econ.)。1955年法政大学経済学部助手、同助教授、同教授を経て1996年定年退職。2014年没。専門は金融史。
主要業績に、<i>The Decline of Inland Bills of Exchange in the London Money Market 1855-1913</i> (Cambridge : At The University Press,1971)、『国際金本位制とロンドン金融市場』(法政大学出版局、1980年)、<i>The Origins of International Banking in Asia: the Nineteenth and Twentieth Centuries</i&g…
内容説明
19世紀末から20世紀初頭のアジアを舞台に繰り広げられた、国際銀行の活動の実態と経済発展のメカニズムを、類例なき緻密さで解明する超大作。
目次
第1編 グローバリゼーションと国際銀行(第一次グローバリゼーションとアジアにおける英系国際銀行;国際資本移動と国際労働移動―1870‐1913年;海底電信ケーブルの敷設と国際銀行 ほか)
第2編 英系国際銀行(国際銀行の前史;東洋銀行―1842‐1884年 ほか)
第3編 非英系国際銀行(ドイツ銀行・独亜銀行―1870‐1913年;露清銀行・インドシナ銀行―1896‐1913年;横浜正金銀行―1880‐1913年)
著者等紹介
西村閑也[ニシムラシズヤ]
法政大学名誉教授。1953年東京大学経済学部卒業、同大学大学院社会科学研究科修士課程修了、1969年ロンドン大学(London School of Economics and Political Science)大学院経済学研究科博士課程修了、Ph.D.(econ.)。1955年法政大学経済学部助手、同助教授、同教授を経て1996年定年退職。2014年没。専門は金融史
鈴木俊夫[スズキトシオ]
帝京大学経済学部教授、東北大学名誉教授。1971年慶應義塾大学商学部卒業、同大学大学院商学研究科修士課程修了、同博士課程単位取得退学、1991年ロンドン大学(London School of Economics and Political Science)大学院経済史研究科博士課程修了、Ph.D.(econ.)。1980年中京大学商学部専任講師、同助教授、同大学経営学部助教授、同教授、東北大学大学院経済学研究科教授を経て現職。専門は英国経済史・経営史、国際銀行史
赤川元章[アカガワモトアキ]
慶應義塾大学名誉教授、千葉商科大学大学院客員教授。1965年慶應義塾大学商学部卒業、同大学大学院商学研究科修士課程修了、同博士課程単位取得退学。博士(商学)。1970年慶應義塾大学商学部助手、同助教授、1978年銀行史研究所(フランクフルト)訪問研究員、1985年慶應義塾大学商学部教授、2001年ケルン大学経営経済学部客員教授、2007年帝京大学経済学部教授を経て現職。専門はドイツ金融史、証券経済論、移行期経済論(中国・東欧)、社会経済学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
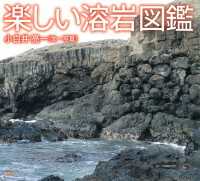
- 電子書籍
- 楽しい溶岩図鑑





