目次
第1章 恋愛―本質と変容(恋(エロース)する人間―プラトン哲学から恋愛の本質を考えよう
恋愛モバイルとモバイル恋愛)
第2章 恋愛―フランスと日本(文学と愛の情景―出会いと告白;江戸時代における恋愛模様―浮世絵から探る)
第3章 恋愛―形象と色彩(永遠をめぐる物語―乙女チック・マンガにおける恋と未来;奈良絵本・絵巻に見る恋愛)
第4章 恋愛―展開と進化(イスラーム世界の恋愛・結婚・離婚―アラブ史の観点から;恋における「遺伝子vs脳」)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鵜殿篤
0
大串尚代「永遠をめぐる物語」での論考は、眼鏡学にも参考になる。少女マンガで「眼鏡を外すと美人」のようなクソのような物語を見ることがあるが、このような物語はアメリカ的精神と近い可能性があると思っている。というのは、もともと日本やヨーロッパには「眼鏡を外して自己実現」という考えは見当たらないのに対し、アメリカではスタンダードであるように見えるからだ。少女マンガに対するアメリカ文学の影響を緻密に調べていくと、「眼鏡を外して自己実現」というゴミのようなエピソードの由来が見えてくるかもしれない。2017/11/12
さき
0
たまたま手にとった本だったのだが、 今年お世話になっている先生も書かれていて、ほほ~、と。 実際に授業で生で聴いていることが本になったって不思議な感じ。2012/11/18
まめはち
0
恋愛を客観的に学問として科学するのは目新しい試み。恋愛をいかに成就させるかというプロセスも社会の変化とともに変化する、そんな当たり前だけど普段考えもしないことを気づかせてもらえました。 社会学からのアプローチにもあるように、かつての恋愛には時間をかけた手紙でのやりとり、家族の目と耳を意識した固定電話でのやりとりがありましたが、現在は携帯電話のおかげで瞬時に個人と個人でつながって便利になりました。でも、心が籠っていて、筆跡を眺めながら何回も読み返せるラブレターや電話をする時の緊張感ってやっぱり良かったですね2011/07/01
サイコ
0
アカデミックな恋愛討論会のまとめ。「ラブレターを書く男はサマにならない」という講義は興味深い。これは19世紀のフランス文学・絵画を例にとっているが、現代日本でもラブレターを書く(メールで告白する)男性はモチーフとしてあまり見受けられないように思われる。恋愛は社会が作り出した文化・慣習を学んだ結果、生み出すことができる関係及び心理であるという意識が強まった。2012/09/27
Hahe0131
0
高校生向け、恋愛という身近かつ関心のあるテーマだったので読みやすかった。自分の大学、学部の公開講座なので知ってる教授が多く、読んでいて楽しかった。内藤先生は普通の講義よりも文字媒体の方が面白いし、石川透先生はその逆だった。特に印象深かったのは納富先生と大串先生の講義。以下納富先生の引用「満たされていない者同士が想いを共有しながら、相手との出会いによって何かを生み出すのが恋愛なのではないでしょうか」以下大串先生の引用「少女マンガ的想像力というものは、自分を肯定してくれる相手との永続性を暗示するものである」2018/08/24
-
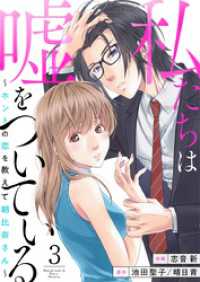
- 電子書籍
- 私たちは嘘をついている~ホントの恋を教…








