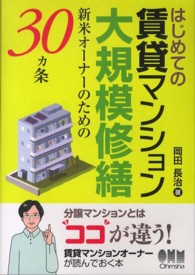内容説明
国内外40の名建築の天井を集めた「天井芸術」の写真集。
目次
浄土寺浄土堂―兵庫県小野市
有楽苑如庵―愛知県犬山市
日光東照宮本地堂―栃木県日光市
角屋―京都府京都市
吉島家住宅―岐阜県高山市
富士屋ホテル別館旧御用邸菊華荘―神奈川県足柄下郡箱根町
ホテルニューグランド―神奈川県横浜市
今村天主堂―福岡県三井郡大刀洗町
横浜市大倉山記念館―神奈川県横浜市
東京都慰霊堂―東京都墨田区〔ほか〕
著者等紹介
五十嵐太郎[イガラシタロウ]
1967年生まれ。建築史・建築批評家。1992年、東京大学大学院修士課程修了。博士(工学)。現在、東北大学大学院教授。あいちトリエンナーレ2013芸術監督、第11回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館コミッショナー、「窓学展―窓から見える世界―」の監修を務める。第64回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞
菊地尊也[キクチタツヤ]
1986年岩手県生まれ。東北大学大学院博士後期課程。建築表現論、展示研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mura_ユル活動
98
「天井美術館」とは命名が良いと思う。読友さんが読んでいたので手に取る。国内の美しい天井の数々、写真中心で。音楽ホールは椅子に座れば、必然的に目に入ってくるが普段は気にしない。本書では建築の専門家によって有名建築の中から選ばれている。個人的には日本の伝統建築がそうであるように、天井を仕上げで覆って隠すのでなく、無垢材のまま仕上げているのが好み。照明などの建築設備もなくしたい。群馬の音楽堂は今年も行ったけれど、ホール内は入れなかった。巻末近くには海外の天井も紹介されている。2019/12/15
リコリス
50
そういえば空は見上げるのに天井ってなかなか見上げなくなったなぁ。阪急のコンコースが好きでよくみあげていた幼い頃を思い出した。圧倒されるような煌びやかなもの、暖かみのあるもの、楽しくなるもの、光に満ち溢れているもの、天井美術館これからはもっとみあげよう。自転車で通った中之島図書館が懐かしい。あの静謐とした空間をわくわくしながらも靴音をたてないようにそーっと歩いた頃の自分を思い出した。思い出の引き出しを開くような1枚にであえるかも。2019/03/11
アキ
47
巻末の40もの天井の写真を下を向いて眺めるというのも乙なもの。見せる天井はみんなびっくりする程個性的。それにしても日本国内だけで数寄屋風・格子・和洋折衷・ガウディ風・バロック・ドーム・ヴォ―ルト・アールデコ・古典主義とこれだけバリエーションがあるのに注目したことはなかったな。天井を見上げて感動した場所は2000年前に建てられたローマのパンテオン。天井に穴があり光が差し込むさまは天からの恵みのよう。できれば京都の角屋か鎌倉の吉屋信子記念館あたりで天井を眺めながらひと晩寝てどんな夢が見れるか試してみたい。2019/01/31
なる
36
美術品そのものではなく、天井。天井の装飾や建築の妙を愛でるという、これはこれで良いところを突いたな、という写真集。そのほとんどが関東寄りで、美術館というより教会や邸宅、文化施設や宿泊施設といった、まさに建物を主役とした焦点の当て方が面白い。やっぱり建物も良いわよね。建築に興味はないけど邸宅や施設の内部を見るのは好きなので可能な限り一般公開しているところは攻略はしておきたい。とはいえ東京と神奈川は既にほぼ制覇していたようなので、残りの関東圏と西日本地区を早急に攻略しなくてはならないと心に誓うのであった。2023/12/31
G-dark
36
床に寝転がって天井を見上げて「あ!あの模様きれい!」と無邪気に楽しんでいた子どもの頃に戻ったような気分になれる本。日本を含めた世界各地の美しい建築物の天井とその解説をおさめた写真集です。和風、洋風、和洋折衷のものなど、建築家の独創的なアイディアや職人さんたちの大胆且つ繊細な技が目の保養になります。わたしはまず「有楽苑」の茶室如庵に惹かれました。全体的にとても渋くて、大昔の日本にタイムスリップしたかのような気分に浸れますし、客座と上座に2種の天井が共存しているという構造が興味深いです。2020/12/07