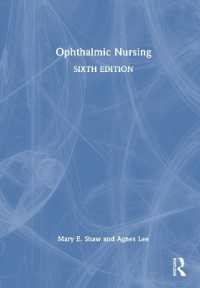内容説明
巨匠ダヴィンチが活躍していた時代、絵具は貴重なものだった。絵具の種類もせいぜい十数種類くらいしかなかったらしい。現在では絵具の種類は溢れ、五百種類以上といわれている。にもかかわらず、なぜダヴィンチの絵は色が氾濫している現在でも輝き続け、そして奥に秘めた豊かな色彩を感じさせているのだろうか。色は光であり、鉱物であり、化学物質である。だから従来よくある色彩学の理論だけでは、絵は描けないのだ。まずは絵具の色に強くなろう!基本となる6つの色から始めよう!そうすれば、少ない色数で豊富な色感を表すことができるのだ。
目次
第1章 色の基本―色の原理原則と絵具の色(概念としての色;概念上の色の性格 ほか)
第2章 色の性格―連結と対立(球体をどのように立体的に表せばよいか考えてみよう;「連結」と「対立」とは何か? ほか)
第3章 色による光とカゲ(時代によって色は変遷する;「光とカゲ」の名画を水彩画で制作する―モネの色彩効果を体験しよう ほか)
第4章 名画から学ぶ色(六大巨匠による9点の名画から学ぶ色!;色の実践―水彩スケッチで試してみよう ほか)
著者等紹介
鈴木輝實[スズキテルミ]
1946年福島県生まれ。1969年太平洋美術学校卒業。1976年太平洋展文部大臣賞受賞。2002年アートポストカード協会設立。現在、彩花堂絵画研究所主宰。アートポストカード協会代表。太平洋美術会会員。日本色彩学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
assa
0
具体的かつ綺麗。絵筆を持ちたくなった。2010/04/16
緑色と風
0
おもしろいほど色の作り方がわかる本。水彩、油絵において具体的な6色の絵の具名で色相環を表現。さらに、野菜を使った色相環も載っている。紅茶を使って、水をたすことで彩度と明度がどう変わるかは絵の具の特性が一目瞭然。これだけでも絵の具の使い方が身体で理解できた。模型と光源を使って、モネ、ルノワール、ゴッホ等印象派の名画の情景を再現し、名画がどのような世界観のもとで色が選ばれ、描かれたかまで紹介されている。光と影の色使いもわかりやすい。水彩、油絵の絵の具にとどまらず、色を選ぶ考え方、感じ方まで影響を受けた。2009/12/05
-
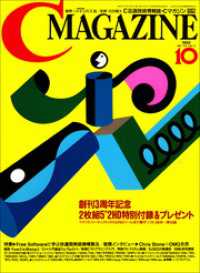
- 電子書籍
- 月刊C MAGAZINE 1992年1…