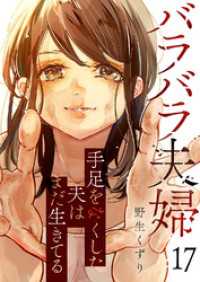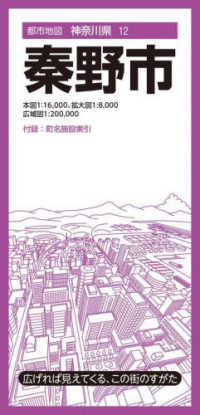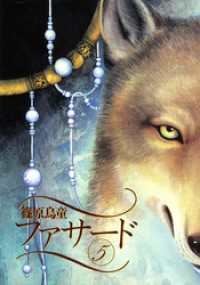目次
第1部 御土居堀ものがたり(京を囲んだ城壁と堀;どうしていま『御土居堀』なのか;秀吉の京都改造;惣構の流行;天正十九年の大動員 ほか)
第2部 御土居堀跡を歩く(「京都惣曲輪御土居絵図」について;九条通~八条通;八条通~七条通;七条通・丹波口;五条通・嵯峨野線「丹波口」駅 ほか)
著者等紹介
中村武生[ナカムラタケオ]
1967年島根県大田市生まれ。大阪府北河内地域(門真市、守口市、枚方市)に育つ。1993年佛教大学大学院文学研究科博士課程前期(日本史学専攻)修了。中近世都市史(惣構論)、史蹟空間論、明治維新史を研究テーマとする。佛教大学・花園大学・天理大学非常勤講師。京都大学人文科学研究所共同研究員(近代京都研究班)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
69
何の予備知識も無く、北野天満宮神苑の御土居堀に登って「これは凄い」と感動した小学生の頃の経験を思い出した。京都新聞の連載コラムを纏めたものであるが、それがかえってまとまりのつかなさに繋がっている。2024/11/23
遼(haruka)
1
日本の都市景観が明治維新後たったの150年で全く違うものになってしまったのは、日本文化を敬愛する者の一人として残念でならない。筆者は最後、「相続税」について触れた。以前、別の方が、日本の伝統建築の保存に関し「建築基準法」の問題点に触れていたのを思い出した。つまり日本という国は、自らの法律でもって、自らの文化を蔑ろにしているのはないか。御土居で囲われていた頃の京都は、どんな風だったろう。我々はわずか1世紀半で、自分たちの歴史に触れる術の一つをほとんど消してしまった。2018/11/14
犬丸#9
1
★★★☆☆「読み物」としての詰めが甘い。文章は単調で同じ話が何度も出てくる。リズムもよくない。 御土居にターゲットを絞ったのはいいけれど、見方自体も些か近視眼的。もうちょっと多角的な視点があればもっと楽しい読み物になったと思う。 でも、この本の中には、御土居に対するパトスがぎっちり詰まっている。「書物」としての完成度は低いかもしれないが、行間から著者自身の熱烈な思いがあふれ出している。評価はあまり高くできないけど、でも、楽しい読書時間を持てたことも事実。きっと著者の先生って、面白い人だろうなあ。 惜
じょういち
1
タイトルの通り「堀」という表現に拘泥しているが、東側にはほとんど堀はないのでそこまでこだわる意味が分からない。随所に破壊への憤慨や保存の請求が見られるが、どれも感情的で建設的でない。秀吉が造り、幕府が管理したが、それでも市民に近いものだったという強調があったが、そう言うなら現代の市民とてそれぞれ事情があって、その土地を利用しているに過ぎない。案内板で啓蒙しろというのも目立つが、そもそも興味をもつ人は最初から勉強しているし、興味ない人は読まない。御土居に関する知識は増えたが、学術的には芳しくない。2015/08/03