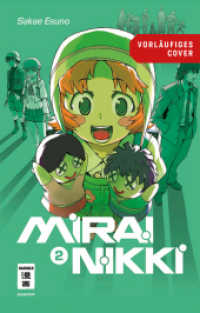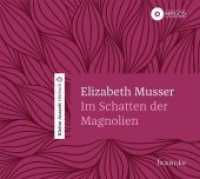内容説明
3・11以降、被災地であらわになった日本の縮図。被災者の心の叫びを聴け!気鋭のジャーナリストが迫った東北被災地・被災者の1年。大手メディアによって増幅された復興美談・絆美談に一石を投じるリアルルポ。
目次
はじめに 絆ではなく歪が見えた大震災
第1章 被災者のリアル
第2章 見えない恐怖に翻弄される被災者
第3章 ボランティア迷惑論のウソ
第4章 自己満足ボランティア
第5章 まとまらない被災地、復旧にこだわる被災者
第6章 始まった自立支援のかたち
あとがき3.11を教訓にし、日本が変わる契機に
著者等紹介
笠虎崇[カサコタカ]
年間8万枚の撮影、年間60万字の執筆をこなす、写真も撮影できるライター=カメライター(ライター&カメラマン)。ネット上では「かさこ」のペンネームで活動。世界各国、日本各地を飛び回り、取材・撮影を行う。2000年にホームページ「かさこワールド」を立ち上げ、ブログを毎日更新。1975年生まれ。1997年中央大学法学部卒業後、サラ金大手アイフルに就職。不動産担保ローン部門に勤務2年間で約10億円融資するトップセールスマンとして活躍。1999年退職後、4ヵ月、アジアを放浪。帰国後、編集・ライター・カメラマンに転身した異色の経歴を持つ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
42
副題は被災地のリアルとボランティアの功罪。先の震災で多くのボランティアが活動されたことは記憶に新しい。その活動が被災者との間で溝が生まれることがあるということ。被災者にとって何が必要なのか、それは具体的にどのようなことがどれくらいということが明確にならないまま活動すると逆に被災者にとって大きな負担にもなることを知った。被災者のため絆が大事だ、絆を深めるために慰問したりイベントを行い元気だ、勇気だという世の中に疑問を持っていたので同感する内容もあった。被災者にならないとわからないことはあまりあると感じた。2015/11/28
MADAKI
1
東日本大震災で多数のボランティアが動員されたことに端を発して、書かれた本。ボランティアの本質は自己犠牲お思われがちだが、実際には受け手側のニーズや思いに寄り添わないと有効とは言えない。当たり前だが重要な事実に気づかせてもらえる。
ブブジ
1
何より福島県いわき市の震災時の不手際が際立った印象を受けました。ボランティア活動の“功”と“罪”を浮き上がらせた内容で納得もありましたが、いくら筆者が"被災者の視点で"と訴えていても、やっぱり都会の人の目線だなぁと感じました。本当に被災者が高台に集団移転することが現実的なのでしょうか。今、都会に暮らしている人々が今すぐ住んでいる土地を捨てて高台に移転しろと言われたら、自分達にはそんなことができるのでしょうか。何が何でも高台移転というのは、高齢化で足腰の弱った老人たちには酷でしょ。何か別の方法が必要では?2013/02/22
-
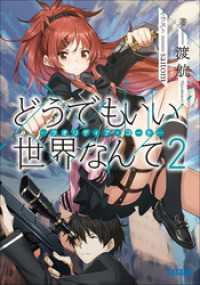
- 電子書籍
- どうでもいい 世界なんて2―クオリディ…