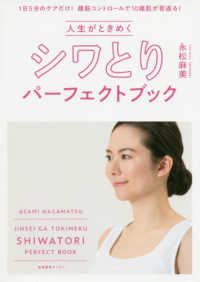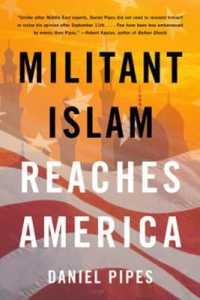内容説明
「追究の鬼」を育てる指導で名をはせた教育界のカリスマが語る、やる気を引き出す技術と極意。
目次
第1章 誘導し、ふくらませる技術(多く伝えようとしたら、少なく教えよ;すぐれた教え方は「教わった」という感覚を持たせない ほか)
第2章 考えさせ、追究させる技術(先回りする人には注意する;「わかったつもり」を「わかる」に変える三つの条件 ほか)
第3章 引き込み、注目させる技術(何を材料に選んだかで七割が決まる;だれでもかならず食いつくネタの条件 ほか)
第4章 モチベーションを高め、才能を伸ばす技術(他人に紹介してもらうようではよい関係はつくれない;グループを代表するモデルを決める ほか)
著者等紹介
有田和正[アリタカズマサ]
1935年福岡県生まれ。教材・授業開発研究所代表、東北福祉大学教授、前愛知教育大学教授。玉川大学文学部教育学科を卒業後、福岡県の公立校、福岡教育大学附属小倉小学校を経て筑波大学附属小学校に赴任する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
き
44
新年度が始まる前に、教育について改めて考えたいと思い読んだ。教える技術とは「教え惜しむ」技術であり、教えることの要諦は「いかに教えないか」にある。今の自分にとってまだまだその境地は遠いが、一歩でも近づけるよう努力を続けたいと思った。2021/04/03
ポチポチ
6
【コメント大歓迎✨】 再読。この本、定期的に読みます。 教え上手ってどんな人? その答えがわかります。 ただ答えを伝えるだけでは不十分で それは直線的に説明しているだけ そうではなく考えるプロセスを持たせる 議論したり、調べたりした上の 結論として答えを出させる はてなを生み出す『発問』や『教え惜しみ』で 調べたい!知りたい!学びたい!を触発させる 問いかけるだけでなく、惑わせ、揺さぶったりする、知らないフリもする 教材とネタの準備が8割 身になることと疑問は7対3が黄金比 【audiobook聴き放題】2023/10/21
村上 飛鳥
6
「何を教えるか」を考えるということは、同時に「何を教えないか」を考えるという事。 優れた教師はその塩梅がうまい。どうしても全部を教えがちであるが、自分の力で考えたと思わせる教師が良い。 著者の思慮深さにため息がでる。2017/05/28
あいぎす
6
教えすぎない。これほど深く難しいことが他にあるか。自分が昔そうだったが子供が躓かないように、わからないと言われないようにしていた。だが、本気で目の前の生徒を伸ばすなら自分で考える力をつけさせなければならない、何度躓こうと励まし続け頑張らせる以外に道はない。この本からは溢れ出るほどの先生の情熱を感じる。添削で赤を入れすぎない、板書は単語に近いくらい絞って書く、形容詞は出来るだけ省く、授業は面白く笑えるものにするなど。ノートは早く汚く書けと言う先生は初めて。目的と手段を間違えない、教育者の教科書にすべき本。2017/02/24
T.E
6
誰もが認めるプロ教師・有田和正先生による万人向けの教育書。 多くの実践例の分かりやすい解説を通して、「教えるということは、出来る限り多くの知識を詰め込むことではなく、自分で問い、考え、行動できる人間を育てること」という先生の考え方が一貫して主張されている。 子どもの「なぜ?」「どうして?」という疑問に火をつける発問や教材作りは考えさせる学習活動の基本であり、教師はそうした活動のための「ネタ」探しや発問の考案に力を注がなければならない。 また、子どものことをよく把握することの重要性も共感出来た。2011/10/06
-
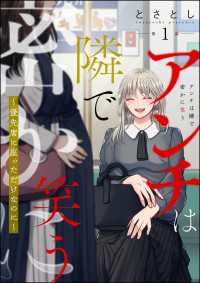
- 電子書籍
- アンチは隣で密かに笑う ~優先席に座っ…
-

- 電子書籍
- 粛正配信 異世界で英雄だった鬼畜賢者は…