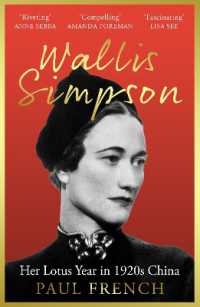内容説明
「伸びる可能性」を持っているのは、“アイデア偏差値50以下”の人なんです。ロングセラー『考具』の著者が熱弁をふるった、「人をうならせるアイデアを出す講義」完全収録!
目次
1章 アイデアとは何か?(「考える」は、スポーツである―創造力はトレーニングで鍛えられる;「考える」のルールとは?―アイデアとは選択肢である)
2章 アイデアが湧き出る仕組みをつくる(選択肢を出す 個人編―チームプレーの本質は、魅力的な個人プレーの連続である;体験を増やすトレーニング―普通の生活で発想力を鍛える)
3章 アイデアを育てる(選択肢を出す チーム編―もう出ないと思ってからもアイデアは出る;最適なアイデアを選ぶために―選択基準はどう設定するのか)
4章 アイデアから企画へ(企画に整える―「わがままなアイデア」が丸まって「思いやりある企画」になる;企画書を書く―企画書は読み物であり、見物である)
著者等紹介
加藤昌治[カトウマサハル]
株式会社博報堂勤務。情報環境の改善を通じてクライアントのブランド価値を高めることをミッションとし、マーケティングとマネジメントの両面から課題解決を実現する情報戦略・企画の立案、実施を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はち
1
@85アイデアは分けて考える。ワガママでよく否定しないアイデア出しと、選択と、企画として整える。こう捉えるだけでコリ固まった脳が開いていく。発想力とかユニークさがないと思っている人必読。2013/09/27
ぱぴんちゅ
0
アイデアだしの手法は一般的なものだったが、「選ぶのはとても難しい。だからリーダーの仕事になる」という一文にグッときた。選択を失敗する理由には「見る目がない」からか、「選択基準そのものの設定」ができなかったから、の2つがある。前者を理由にしがちだが、後者の対顧客、対社内での振り返りをどれだけできているだろうか?2014/02/28
Nao Shimoguchiya
0
わがままをいかに多くだせるか、それらを選択し落とし込む。自らの体験、知識がアイディアとなっていくこと。アイディアの出し方という本をわかりやすく書かれた本だとおもう。2013/11/12
一龍
0
『考具』の加藤さんの新刊。かなり文字数多く、ボリュームがありますが、実況中継の名の通り「講義」形式で楽しみながら読むことができます。 アイデア出しと言うと非常に特殊な才能が必要のように思われがちですが、著者曰く「アイデアを出すことはスポーツと同じ。練習すれば誰でも上手にできるようになる」とのこと。 その練習方法を本書では学べます、 2013/10/15
nutts
0
「考具」で取り上げた発想方法を、実際にどんな勘所をもってどの程度の成果物をあげるよう使いこなしたらよいのか、ワークショップをやっているような感覚で説明してくれる。実践編にしたら逆に、感覚的な部分がちょっと分かり難い感じ。(味はこんな感じで調えて、と言われるよりは、塩コショウを少々、醤油小さじ1杯、と説明してもらう方が分かり易いなぁ)2013/10/21