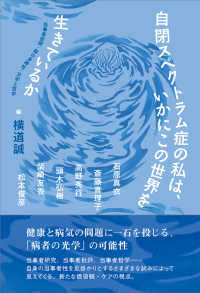内容説明
多岐にわたる装いの各特徴や意義をバランスよく解説。くわえて、コスプレや化粧療法といった分野での装いのはたらきにも言及。装い研究の広さ、深さ、おもしろさがわかる入門書。
目次
装い探訪
第1部 装いの種類(メイクアップ;スキンケア;衣服(アウター)
衣服(インナー)
ピアッシング
イレズミ:彫り物・タトゥーイング
美容整形
体型:痩身
ヘアスタイリング・脱毛
しぐさ・歩容
言葉)
第2部 装いの関連テーマ(コスプレ;化粧療法;装い起因障害;装いの低年齢化;装いの文化差)
装い再訪
著者等紹介
鈴木公啓[スズキトモヒロ]
1976年岩手県に生まれる。2008年東洋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。現在、東京未来大学こども心理学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くさてる
21
「装う」ということ。それは化粧、スキンケア、衣服から入れ墨、美容整形や痩身、仕草や言葉までも包括する人間にとって大事なテーマなんだということを感じた。そしてそこから派生する、コスプレや化粧療法、装いの低年齢化などの課題もまた面白い。ひとつひとつのテーマがまとまり良く語られていて、教科書的に読みやすいです。2021/03/20
小木ハム
12
試合でのフェイスペイントがもたらす心理効果を調べているうちに出会った本。化粧に限らず、外見を加工することは「対自的=自分のため」と「対人的=他者のため」の2つのルートがある。装うことによる高揚感はコルチゾールを低下させるし、社会的立場を示す記号でもある。本書はいわゆるメイクアップだけでなく歩容(個人の歩行特徴)であったり用いる言葉や刺青、コスプレなど、古今東西の装い文化について多岐にわたった研究報告が掲載されており参考になる。外見を装うことは「自己を拡張するもの」という表現に得心がいきました。2024/08/18
aoyami
2
『装い』を「さまざまな道具や手段を用いて身体を整え飾り外観を変化させること、およびその結果としての状態」と定義していて、美容領域だけでなく、歩き方、話し方(文章)、しぐさまで、幅広い調査のデータが集約されていてとても面白かった。装いとは、個人的な充足がありつつも、他者に見られることを前提としてなされる行為で、社会や特定の集団との関係性に影響を及ぼそうとする心理が働いていること、しかも時と場所によって良いとされるものが変化するので流動的であることがよくわかった。装いは文化として奥深い領域なのだと知った。2022/03/23