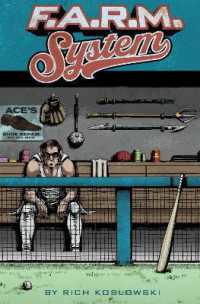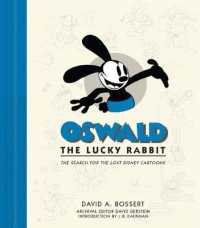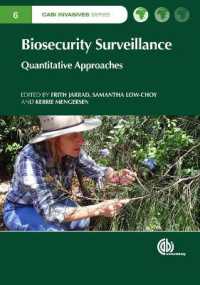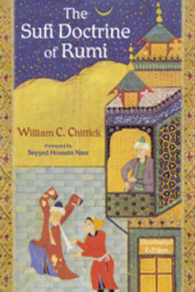出版社内容情報
これまでの欧米中心の研究知見の単なる紹介ではなく,日本人研究者の視点で,理論と実践の両面から自己調整学習研究の現在を包括的・体系的に捉え直すとともに,今後の研究の課題や方向性を展望する。教育心理学や実践研究での知見を統合し,発達段階やカリキュラムと関連づけながら,特に実践的提言を行うことを重視した。
目次
第1部 自己調整学習の基礎理論(自己調整学習理論の概観;自己調整学習方略とメタ認知;動機づけ;自己調整学習における他者;学業的援助要請;自己調整学習研究における文化的考察)
第2部 自己調整学習と教育実践(国語教育における自己調整学習;算数・数学における自己調整学習―日本の児童・生徒のつまずきの原因とその支援策を中心に;理科における自己調整学習―誤ルールの修正に焦点を当てて;英語教育;日本語教育における自己調整学習;自己調整学習を育てる大学教育;自己調整学習と家庭学習)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホシ
21
お仕事本。ライフハック本とか読んでましたけど、本書こそしっかり読むべきでした(学術書だから難解だけど)。第6章の秋場氏の論考が興味深った。「自己調整学習スキル」とか「自己効力感」といった概念は西洋の研究に依るものが良しとされ、それが他の地域にも適用されるべきと見る向きがあるが、その地域独自の(東洋には東洋独自の)自己調整学習スキルや自己効力感があって、それが考察されるべきという論考。確かにそうだと思う。学習者中心教育研究の理論に従って初期原理を開発すれば良い、というアイディアが閃く!要熟読。2023/10/16