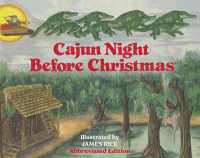目次
文章理解:結束性と意味の創造
第1部 文章理解の認知過程(単語の読みと心的辞書;語の意味と概念;文理解の過程;文章理解における方略とメタ認知;読解過程における情動と動機;文章理解のコンピュータ・シュミレーション;文章理解を支える脳神経メカニズム)
第2部 読むことの発達・熟達(幼児期における読解の発達;児童生徒における読解の個人差;読みの生涯発達)
第3部 教育における文章と活動(学習を支える多様なテキスト;科学理論を読み取る、理論を学ぶ;文学を味わう;第二言語による文章理解;マンガの表現内容・表現構造と読み;総合学習と読みの学習;批判的に読み、自分の主張へとつなげる国語学習;読みの授業づくり)
著者等紹介
大村彰道[オオムラアキミチ]
慶應義塾大学・文学部教授。東京大学大学院・教育学研究科名誉教授
秋田喜代美[アキタキヨミ]
東京大学大学院・教育学研究科助教授
久野雅樹[ヒサノマサキ]
電気通信大学・電気通信学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
take
1
類書『文章を理解するとは』(甲田直美)の後に読んだ。「高校・予備校の読解授業で実践的に生かせる方法論を学びたい」という私には甲田氏の著書の方が適していたが、幅広い視点から文章理解を考察しており、「1つのクラスには読解力が少なくとも5学年以上離れた者が在籍している」というデータ等、幾つかの興味深い情報は得られた。2017/03/09
satochan
1
学生に日本語や数学を教えるときの参考になるかなと思い、この本を読んだ。文章を理解できないと、問題を読み解くことも、本を理解することも難しい。でも、変数が多すぎる。変数が違えば方略も変わる。状況に応じてパターンを変えてやっていくしかない。本書は章ごとに読書案内とか引用文献がついているので、本書を読んで気になったら、別の本を読んでみることができる。序章の文を理解する過程の人の頭の中の構造が気になった。実際どうなっているんだろうか。気になる。2017/02/08
RKG
0
フムフムと興味深く読める。 2021/04/15