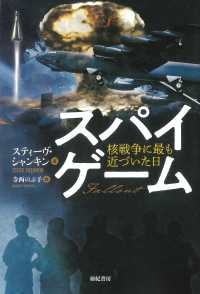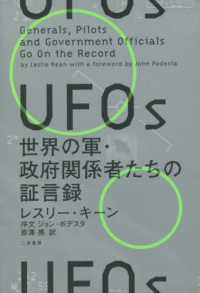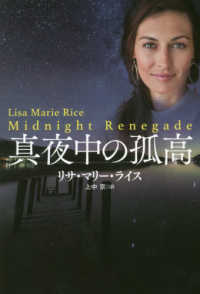内容説明
支援のために理解する知的障害児の心理学。知的障害児ってどんな子ども?その子どもたちへの支援ってどんなことをするのだろう?知的障害児の教育をはじめて学ぼうとする人たちのために、心理学のジャンルごとに何が研究され、どんなことがわかってきたかをやさしく解説しています。基礎知識としての心理学用語、検査法、実験データやデザインを豊富に紹介。さらに、コラム、実際の支援事例を取り上げた「事例から学ぶ」など、基礎から応用まで幅広く扱っています。障害児教育に出会ってまず最初に読みたい一冊。
目次
1章 知的障害に関する基礎知識(知的障害の定義;知的障害の分類;知的障害のアセスメント)
2章 知的障害における心理機能と発達支援(知覚;学習;音声言語 ほか)
3章 知的障害に関連する諸障害(てんかん;自閉症;ダウン症 ほか)
著者等紹介
小池敏英[コイケトシヒデ]
1953年生まれ。現在、東京学芸大学教育学部教授(障害児教育学)
北島善夫[キタジマヨシオ]
1963年生まれ。現在、千葉大学教育学部助教授(障害児教育教室)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう
3
実験が多く、IMRAD形式の文章ではないので読みにくい。 心理学実験で実証された内容を支援に活用できると考えたいところだが、非日常的な条件で得られた結果から導き出される支援がどこまで日常生活に適応可能かは疑問が残る。 第一章で紹介されていたアメリカ精神遅滞学会の、診断・分類・サポートシステムを決定するための3段階の過程にあるように、サポートの定義や当事者が必要とする支援の種類・定義などを踏まえると、第二章にまとめられている心理学実験の結果は実際の支援の現場からかなり乖離しているのではないだろうか。2025/06/12
みあき
1
勉強。2014/07/02