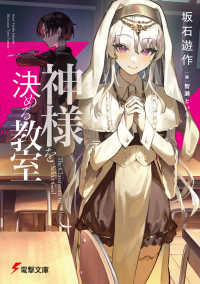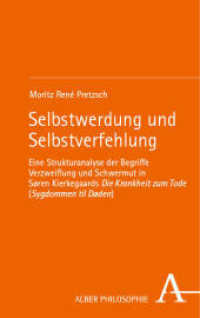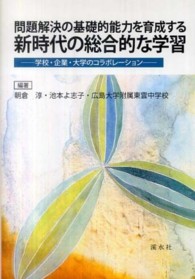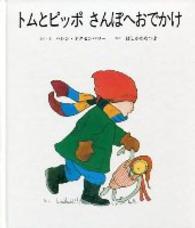- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
目次
第1部 大津いじめ事件からみえてきたもの―いじめ防止対策推進法の背景(人間存在への興味と関心―大津の中2男子いじめ自殺を取材して;「いじめ」による子どもの自死を防ぐために―いま、教師は何をすべきか)
第2部 いじめと向き合う教育の現場―その試み(いじめ予防はどのようにあるべきか―「弁護士によるいじめ予防授業」を通じた考察;いじめと向き合う教育実践―子どもと保護者そして教材)
第3部 いじめをなくす学校づくり・学級づくり(「いじめ」のない学校を作るにはどうすればよいか―「いじめ防止」に向けた北欧諸国の取り組みをもとにして;難題と向き合うもうひとつの学級づくり―子どもの現実と「学級崩壊」現象を重ね合わせて)
第4部 いじめのない学校と教育への想い(自死する子どもがいない学校と教育を実現してほしい)
著者等紹介
近藤庄一[コンドウショウイチ]
1947年生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授、早稲田大学教師。教育研究所所長。専門は数学(代数学)
安達昇[アダチノボル]
1949年、京都府生まれ。元小学校教諭、早稲田大学教師教育研究所招聘研究員。「人権・いのち・人間関係」をキーワードに参加体験型の学習方法を取り入れた教材開発をしています(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
17
2014年刊。いじめ防止対策推進法施行後に出版された。いじめの背景には子どもの権利委員会から指摘されているような、学校の過度な競争主義によるストレスや管理主義があり、子どもの権利侵害という観点から構造的な問題としていじめ問題を捉えるべきだとしている。また、学校だけでいじめを解決することは困難であり、福祉との連携も求められてくる。個人的には菊地論文にあるように、社会全体が新自由主義の価値観に染まり、学校が進学塾と同じ評価システムを導入することの弊害をあらためて強く意識することになった。2025/06/08
鵜殿篤
0
【要約】いじめとは、被害者から生きる力を根こそぎ奪う人権侵害です。人権という観点を大事にし、子どもたち自身が当事者として主体的に関わることが大切です。 実際の事件の分析や、弁護士によるいじめ防止の授業例、さらに北欧での取り組みなどを参考に、いじめを防止する方策を考えます。根本的な問題は、近代の原理が子どもに多くの負荷を与えていることです。2019/09/12
-

- 電子書籍
- トランスヴィーナス~訳アリ女神に出会っ…