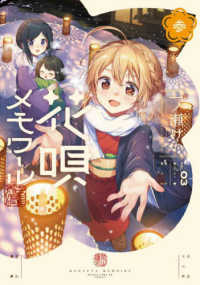内容説明
国語という教科が成立したのは、1900年のことである。それ以来、国語科の「教科内容の系統性」は曖昧なまま放置され続けてきた。そのことは、日本で最も影響力のある教科内容「学習指導要領・国語」にわかりやすいかたちで顕在化している。なぜ、小学校3・4年生で「登場人物の性格や気持の変化」を学び、5・6年生で「登場人物の相互関係」を学び、中学校3年生で「登場人物の設定」について学ぶのか。この順序にどんな必然性があるのか?「構造」「形象」「レトリック」「論理」「吟味」のキーワードを核としながら、「教科内容の系統化」について大胆な試案作成を試みる。
目次
1 国語科の教科内容の「系統性」を解明する(問題提起;物語・小説の系統性 ほか)
2 「系統性」を重視した新しい国語の授業づくり(詩の技法を生かした授業―「比喩」「反復」をどう読むか;新聞記事を読む力を育てるNIEの授業―京北オリンピック・聖火リレーの記事を読み解く ほか)
3 小学校・古典「竹取物語」の1時間の全授業記録とその徹底分析(『竹取物語』(冒頭)―かぐや姫の発見―の1時間の全授業記録
授業へのコメント(似た言葉の違いを考えることの大切さ;小学5年生の古文の授業方法「何でだろう」と謎解きをするように古文を読ませる) ほか)
4 国語科教育の改革―教科内容の「系統性」に関する提言(言語思考力育成系統化の一考察―『モアイは語る』を例に推論(対比と類比)の方法
「系統性」の複雑性をめぐるメモ ほか)
5 国語の教科内容の「系統性」を考えるための読書案内―私が勧めるこの一冊(『“解釈”と“分析”の統合をめざす文学教育』(鶴田清司著)
『西郷竹彦文芸・教育全集3 国語科の全体像』 ほか)
-

- 和書
- マンガ研究13講