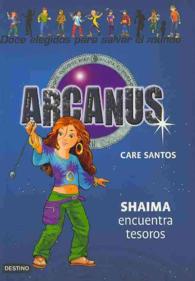内容説明
「調べ」たら、世の中のことはわかるものだろうか。「調べ」さえすれば、世の中のさまざまな事象を正確にとらえることができるものだろうか。その「調べる」の中身がまずは問われるべきであろう。本ブックレットでは、「調べる」という認識枠組みにおいてどのような知識が必要とされるのかを説明してく。また、認識のための作業において、どのようなことをしていかなければならないのかを具体的に紹介していく。
目次
調査デザインの選択
仮設から変数へ
調査の実施方法の決め方
対象標本の設定
標本の抽出
無作為抽出の方法
調査票のつくりかた:体裁と質問文
調査票のつくりかた:回答の選択肢
調査の流れ
面接・留置調査と郵送調査の実際
調査票を回収したら
調査票からデータへ
回収率
著者等紹介
西野理子[ニシノミチコ]
1963年岐阜県生まれ。現職:東洋大学社会学部准教授。早稲田大学第一文学部人文専修卒業、早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程単位取得退学。専攻は家族社会学、ライフコース論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハンギ
0
下手な入門書よりはいいかな、と思って読んでみました。シリーズの二番目の本だけど、別に最初の本を読まなくても理解できる。たぶん離婚問題やジェンダーなどの分野で調査をされた方が書いていて、そういう事例も少し出てくる。技法よりもノウハウの部分が出てくるので、勉強になりました。夫の方に調査をお願いしても、奥さんが書いてしまう事例があったり、正直無作為抽出の電話調査であっても、その家の「誰」が出るかによって調査結果も変わってしまう。根掘り葉掘り聞きたい時は知人やそのツテを頼る、などが望ましいらしい。2012/10/29