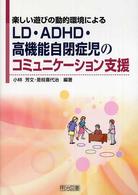目次
第1章 商品経済の発達―産業革命への道
第2章 資本制生産の展開
第3章 独占資本の形成・発展
第4章 国民所得
第5章 財政
第6章 貨幣と金融
第7章 国際収支と国際金融
第8章 戦後世界貿易の展開
第9章 外国為替―制度の変遷と市場相場の変動メカニズム
第10章 現代の金融と貿易
著者等紹介
西村はつ[ニシムラハツ]
兵庫県神戸市生まれ、法政大学経済学部卒業。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在、湘南工科大学客員教授。主要業績に『両大戦間における金融構造』(共著、御茶の水書房、1980年)。『日本金融論の史的研究』(共著、東京大学出版会、1983年)。『近代日本の商品流通』(共著、東京大学出版会、1986年)。『地方財閥の展開と銀行』(共著、日本評論社、1989年)。『近代化の国際比較』(共著、世界書院、1991年)。『近代交通成立史の研究』(共著、法政大学出版局、1994年)。『戦後地方銀行史[I]成長の軌跡』『同[II]銀行経営の展開』(共編著、東洋経済新報社、1994年)。『概説・経済学』(学文社、1994年)。「金融危機と長野県金融界」地方金融史研究会編『地方金融史研究』第30号(1999年3月)所収他
吉田賢一[ヨシダケンイチ]
山形県上山市生まれ、北海道大学経済学部経済学科卒業。和歌山大学大学院経済学研究科修士課程、北海道大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、工学院大学工学部助教授。「金本位制度の自動調節作用について」『工学院大学共通課程研究論叢』第35号―1号(1997年10月)および第35―2号(1997年12月)所収。「利子率の変動と貯蓄・投資理論」『東京経大学会誌』第207号(1998年1月)所収。「貨幣供給の内生性とインフレーション」中央大学『商学論纂』第39巻第5・6合併号(1998年5月)所収。「『IMF体制』崩壊の論理―管理通貨制下の為替相場の研究(その1)―」地方金融史研究会編『地方金融史研究』第28号(社団法人全国地方銀行協会、1997年3月)所収。「変動為替相場制と購買力平価説―管理通貨制下の為替相場の研究(その2)―」同上誌第29号(1998年3月)所収。「レーガノミクスの経済的帰結―管理通貨制下の為替相場の研究(その3・完)―」同上誌第30号(1999年3月)所収他。「『プラザ合意』の経済的帰結―『購買力平価』の悪戯―」日本金融学会編『金融経済研究』第16号(2000年1月)所収。「金融危機下の北海道金融界と銀行合同―百十三銀行・(旧)北海道銀行・北海道拓殖銀行を中心として―」地方金融史研究会編『地方金融史研究』第31号(2000年3月)所収。「両大戦間における北海道内地方銀行―函館銀行・百十三銀行・(旧)北海道銀行の合同関係を中心として―(上)」同上誌・第32号(2001年3月)所収、他
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 中国市場経済への転換