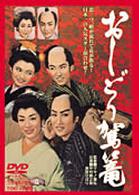内容説明
多様性を前提とした新しい授業として、自由進度学習や自己調整学習、演劇的手法、探究型の学び等に注目が集まっている中、従来からの一斉・説明中心の授業をどう考えればいいのか。価値観が多様化している時代に、授業で教室で何を揃えるのか。一斉・説明中心の授業を多様な視点から問う!
目次
巻頭座談会 一斉・説明中心の授業を改めて考える(鈴木惠子×田中博司×樋口綾香×前田康裕)
巻頭言 「教える」と「学ぶ」に橋を架ける(石川晋)
1 今、一斉・説明の価値を問う
誌上レポート(1) 自分・友達・先生の評価で伸びる子どもたち~飯村友和さんの事前指導「5つの型」による学級づくり~(佐内信之)
2 教えるとは何か、現場から問う
特別対談 1人1台端末と一斉・説明中心の授業を考える~図工が学習者中心のモデルに~(豊福晋平×岩本紅葉)
誌上レポート(2) 読み書きをつくる教室~群馬県太田市立南小学校 久保田比路美さんの国語授業~(井久保大介)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
jotadanobu
0
二項対立的な考えが和らいでいく感覚。個別最適な学習は、型から入るというよりは、子どもが一つの課題に対してより主体的、個性的に協働しながら学んでいく結果実現するものだという感覚の方がイメージしやすい。2025/02/24
U-Tchallenge
0
今回のテーマは「一斉・説明中心の授業再考」である。「個別最適な学び」というキーワードが文科省から出てきて一つのトレンドとなっている。このような流れの中での今回のテーマである。一斉・説明中心の授業を批判的に考えていく内容のように思われるかもしれないが、あくまで再考である。批判的に捉えている論者がいれば、肯定的に捉えている論者もいる。これぞ授業づくりネットワークと言っても過言ではない内容であった。一斉・説明中心をするにせよ個別最適な学びをするにせよ必読の一冊に間違いないだろう。2025/01/03