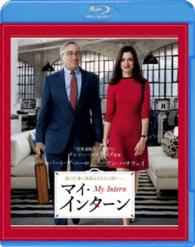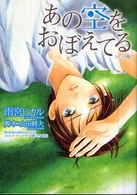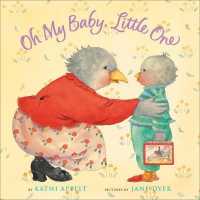内容説明
どんな授業形態であろうが、教師が一言も話さず学習が成立していくことなんてありえない。教師の話し方が授業を左右する。シリーズ第1弾の「教師の話し方」では、話すことに関するさまざまな技術と考え方を、具体的な事例を踏まえて問うた。
目次
第1章 教師にとって最も必要な「話し方」「話す力」(「話す力」を構成する要素)
第2章 話し方にはバリエーションがある(同じトーンで語る教師;話し方のバリエーションは学年・授業に対応できる)
第3章 説得し、納得させる「伝達力」(AL時代の授業でも必要な「伝達力」)
第4章 あなたはどのタイプ?教師の「話し方」タイプ別スキルアップ(淡々あっさりタイプ;ネチネチくどくどタイプ;ふわふわ舞い上がりタイプ;テンションあげあげタイプ;立て板に水タイプ;しっとり落ち着きタイプ;キラキラ笑顔いっぱいタイプ;ほめないし、答えも言わないタイプ)
第5章 ファシリテーターとしての話し方(ファシリテーションとは何か)
著者等紹介
多賀一郎[タガイチロウ]
1955年兵庫県生まれ。追手門学院小学校講師。神戸大学附属住吉小学校を経て私立小学校に長年勤務。元日本私立小学校連合会国語部全国委員長。保護者のために「親塾」を開催したり、若手教師育成のために全国各地のセミナーで登壇したり、公・私立小学校にて指導助言を行っている
佐藤隆史[サトウタカシ]
1961年大阪府十三生まれ。神戸大学教育学部卒業。兵庫県尼崎市(国語)マイスター教員。「教室音読の復権」を合言葉に、近隣の小学校・幼稚園で年に十数回講演や出前音読授業を実施。趣味はダンス。特技は合唱指揮。大学時代、斉田好男氏に4年間指揮法を師事。合唱指揮のメソッドを活かした800人におよぶ全校児童が一堂に会しての「全校音読活動」の指導を10年にわたり継続中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
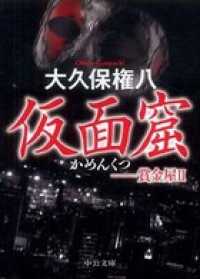
- 電子書籍
- 仮面窟 賞金屋2 中公文庫