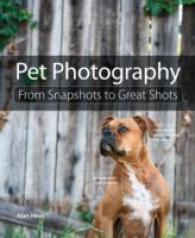内容説明
「変わる学校」と「変わらない学校」―学校づくりがうまく進む学校と、停滞する学校との差はどこにあるのか。“チーム学校”にも不可欠な、学校の組織力を左右するマネジメントの本質をあぶり出す。
目次
第1章 イントロダクション 学校教育の悪循環と好循環
第2章 学びのプロとしての教職員と学習する学校
第3章 組織になりきっていない学校
第4章 学校づくりの成功と失敗の分岐点
第5章 「多忙化」から日本の教育が見える
第6章 組織力を高めるデザインと実践(1) 到達目標の共有
第7章 組織力を高めるデザインと実践(2) プロセスの設計
第8章 組織力を高めるデザインと実践(3) チーム・ネットワークづくり
著者等紹介
妹尾昌俊[セノオマサトシ]
学校づくり×地域づくりコンサルタント。野村総合研究所主任研究員。1979年徳島県生まれ。京都大学大学院修士課程修了(行政学)。これまで自治体等の公的組織のビジョン・戦略立案、行政改革、学校マネジメント等のプロジェクトに多数携わる。教職員向け研修、講演、アドバイス等も精力的に行っている。文部科学省学校評価ワーキング臨時委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミコ
2
★★★★☆「学習する学校」いい。組織マネジメントに必要なものは①到達目標②プロセス③チーム・ネットワークの3つ。学校における「組織」も「マネジメント」も、分かりにくいのに、皆分かったように使っている。①の目標もそれっぽく謳ってるけど、実際は何も言っていない学校が多いとのこと。思い当たる学校が頭によぎる。時々振り返りながら、今後の学校運営に取り組んでいきたい。2020/03/26
HEAVY-BIRD
2
忙しいことは承知していますが、学校の管理職、教育委員会事務局職員にぜひ読んでいただきたい1冊です。2017/08/30
小林だいすけ
2
3つの点が印象的でした。管理職をやる人は最低でもこういう本を月に何冊かは読んで勉強してもらいたいなあ。 管理とマネジメントの違いを理解していない学校管理職が多い、という主張。 教師は教える専門家であると同時に、学びの専門家であるべきなのに、読書量などの統計をみると、教師はあまり学んでいない、という指摘。 仕事の優先順位だけではなく、劣後順位を意識的に考えるべき。という主張。 学級担任としても参考になりますし、将来的にも役立つと思うので忘れないようにしよう。2017/01/30
ぴーたん
2
「変われる学校」と、そうでない学校にはどんな違いがあるか?具体性のある明確な目標設定や、これまでの取り組みの立案はできているか?学校のウェブページを見てみると、「元気な子を育てる」「やさしい子を育てる」など具体性に欠ける目標が多い。また、校長は管理とマネジメントの違いもわかっていないとのこと。年度末の振り返りはしても次につながってないこともある。失敗例のあるあるが多すぎて首がもげるかと思った。この本のFBページもあるし、今月は読書会があったみたいだけど読む前で参加できず残念!勤務先で呼べないだろうか…。2016/12/26
どこかの国語教師
2
2015年、最後の1冊になるかな。組織マネジメントの観点から、学校の改革を語る。学校という場は特殊で、企業と同列には扱えない。けれど、その閉鎖性がなにも変わらず、世の中から取り残される。学校評価制度を導入し、学校目標を立てても抽象論ばかりで具体化しない。結局、教師個人に任せっきりになる。「変わらない学校」のパターンに自分の勤務校がバッチリはまってそうで……。ぜひ、管理職に読んでもらいたい。2015/12/31