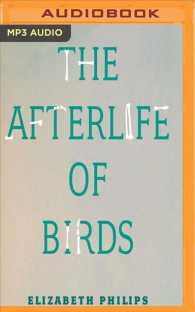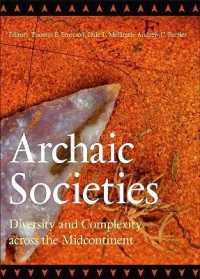内容説明
それぞれの領域ごとのねらい・保育内容を実践化できるよう、具体的な活動に基づいて展開しています。新・幼稚園教育要領や保育指針の趣旨を生かし、事例をわかりやすく解説。現場の保育に応えています。本巻は「言葉」について。
目次
第1章 保育における領域「言葉」
第2章 言葉が育つ環境と生活
第3章 友だちや仲間の中でこそ文字などで伝える楽しみを
第4章 『聞く』と『聴く』
第5章 ことばの遅れと障害
著者等紹介
玉井美知子[タマイミチコ]
東京都生まれ。日本女子大学家政学部卒業。神奈川県立横浜立野高校教諭、同県立青少年センター主事、同県教育委員会指導主事・主幹、県立横浜幼稚園長、県立中原養護学校校長、県立藤沢高校校長、文教大学女子短期大学部教授、日本女子大学文学部教育学科講師、東京成徳短期大学講師などを歴任。その他、教育課程審議会委員(1971~77年)、高等学校学習指導要領改訂協力者委員、幼稚園教育要領指導書作成委員、総理府“青少年の性意識調査企画調査委員、NHK、文化放送、テレビ朝日など番組審議会委員を歴任。新学社日本教材文化研究財団評議員、全日本家庭教育研究会参与講師、同社“文書による教育相談”の担当(’74年より現在に至る)。神奈川県教育委員会教育功労賞受賞(’85年)。著書に「虹子と啓介の交換日記」(’62年)「お母さん合格よ」(’62年)「青年期の探究(I)(II)」(’66年)その他、編著に「新しい家庭教育」(’93年)「わかりやすい家族関係学」(’96年)「新しい家庭教育の実際」(2000年)、共著に「保育内容研究シリーズ3、自然の指導」(’74年)「自然-その指導と実際」(’79年)「領域『自然』の心理と指導」(’83年)ほか
赤松かの子[アカマツカノコ]
現在北区上十条南保育園園長。コダーイ芸術教育研究所会員。乳幼児のわらべうた実践をスタートに会員となり乳児保育、幼児保育の内容を研究。現在はわらべうたの他に乳幼児の数学的思考認識等の発達についての実践を研究。共著に「数あそび『年中編』・『年長編』」
今井和子[イマイカズコ]
20数年間、東京と川崎の公立保育園で保母として働く。保育所を退職後、十文字学園女子短期大学、お茶の水女子大学非常勤講師を経て、現在は東京成徳短期大学教授。全国子どもとことば研究会代表。著書に「ことばの中の子どもたち」(日私幼賞受賞)「自我の育ちと探索活動」「なぜごっこあそび?」「保育に活かす記録の書き方」「私の中の子どもと詩」「子どもとことばの世界」「0、1、2歳児の心の育ちと保育」「表現する楽しさを育てる保育実践」他、共著に「集団って何だろう?」「家庭との連携と子育て支援」
遠藤敬子[エンドウケイコ]
1995年筑波大学人間学類卒業(心身障害学専攻)。’97年筑波大学大学院修士課程修了(教育研究課障害児教育専攻)。’98年より横浜市内の総合病院医療ソーシャルワーカー
後藤範子[ゴトウノリコ]
日本女子大学大学院修士課程修了。幼稚園教諭を経て、現在和泉短期大学講師。保育者を目指す学生に、すこしでも自分の経験が役立つことを願いながら、日々勉強中
高玉和子[タカタマカズコ]
明治学院大学大学院社会学研究科社会福祉専攻博士課程前期課程修了。現在駒沢女子短期大学保育科助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。