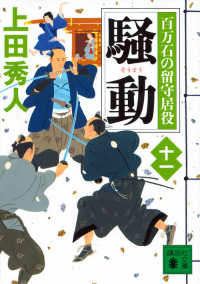内容説明
非公開の個人庭園を含む113庭撮り下ろし。「テーマ→抽象→造形」という作庭プロセスを、古典庭園との比較、半世紀にわたる作風の変遷から解き明かす。
目次
第1部 重森庭園の軌跡(重森生家(天籟庵)
西谷家(旭楽庭)
春日大社1(三方正面七五三磐境の庭)
四方家(海印山荘)
正伝寺 ほか)
第2部 古典庭園と重森枯山水(古典から学ぶ;重森の枯山水はなぜ刺激的か;重森をより深く理解する;芸術家・重森三玲)
著者等紹介
中田勝康[ナカタカツヤス]
1941年長野県松本市に生まれる。1965年信州大学工学部卒業。会社勤務の傍ら古代史に興味を持ち、故原田大六先生に師事。その後、故重森三玲先生を知り、その愛弟子の齋藤忠一先生より日本庭園の見方について薫陶を受ける。現在、各団体の庭園講座講師を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かっぱ
29
【図書館】重森三玲が作庭した約200庭の中から、個人宅も含めて113庭を紹介。写真は残っていても阪神淡路大震災で失われたものや、既に取り壊されたものもある。少年時代から生け花や絵画の勉強をし、18歳の時に自宅に茶室を設計、美術学校に通った後、独学で作庭を始める。全国の庭園を見てまわり、歴史あるものに学びながらも新しい庭造りを行った。やはり最高傑作は東福寺の八相の庭。最晩年の作品である松尾大社の庭園もいい。生涯竜安寺の石庭を超える庭を目指した。社寺だけではなく、個人宅にも目を惹く作品が多い。2014/07/11
-
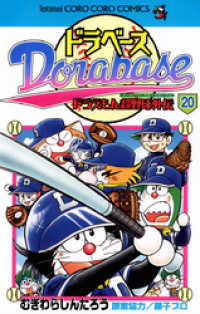
- 電子書籍
- ドラベース ドラえもん超野球(スーパー…
-
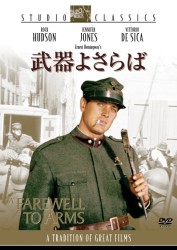
- DVD
- 武器よさらば